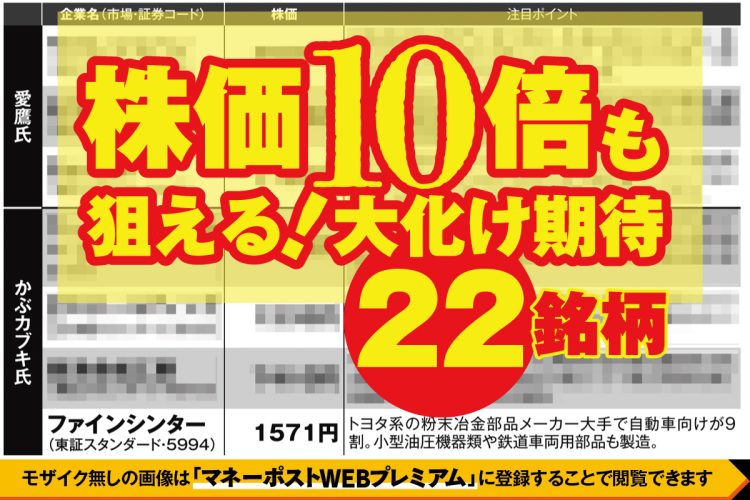更生技術――掘らずに長寿命化を図る
地下に張り巡らされた水道管や下水道管の多くは、高度経済成長期に整備されてからすでに数十年が経過し、いまや更新時期を迎えています。ところが、従来は道路を大きく掘り返して管を交換する「開削方式」が主流であり、工期の長さ、騒音、交通規制、コスト負担など、多くの課題を抱えてきました。
こうした課題を克服する手段として注目されているのが「非開削工法」、とくに「更生技術」と呼ばれる手法です。これは既存の老朽管をそのまま活用し、内部から新しい管を再構築するもので、地表の掘削を最小限に抑えつつ耐久性を確保できるという点で、都市部や交通量の多い場所での工事に威力を発揮します。
代表的な手法の1つが「CIPP工法(Cured-in-PlacePipe)」です。これは、柔軟なライナー(不織布などに樹脂を含浸させたもの)を既設管に挿入し、内部で加圧して密着させた後、熱や紫外線を用いて硬化させることで、管の中に新しい内管を形成する技術です。ライナーは施工現場で成形できるため、曲がりや段差など複雑な形状にも対応しやすいという利点があります。
もう1つの代表例が「スパイラル工法(SPR工法)」です。この工法では、帯状の硬質塩化ビニル製材料をスパイラル状に既設管内に巻き付け、接合部に充填材を注入して強度を高めます。構造的には「管の中に新たな管を組み立てる」ようなイメージで、円形断面以外の管や大口径管にも柔軟に適応可能です。いずれも、既設管の強度がある程度残っている状況での使用が前提となります。
非開削工法の最大の利点は、工事の社会的影響を抑えられる点にあります。道路の掘削が少ないため、周辺住民への騒音・振動の影響が軽減され、交通規制も最小限で済みます。加えて、工期の短縮とコスト削減も見込め、維持管理にかかる負担を大きく軽減する効果があります。
とはいえ、これらの技術にも限界があります。たとえば、既設管が大きく破損し、崩壊の危険がある場合には、内面にライナーを密着させることが困難であり、開削工法を選ばざるを得ない場面もあります。また、施工には専門技術や経験が求められ、地方の小規模自治体では人材確保がボトルネックとなる場合もあります。
それでも、「掘らずに更新できる」という選択肢の存在は、維持管理の新たな地平を切り拓いています。点検・予測・補修という一連の流れの中で、非開削工法は「更新のハードルを下げる」重要な技術であり、人手や財源が限られる自治体にとっては大きな支えとなるでしょう。インフラ維持の次のフェーズは、もはや力業ではなく、技術と知恵で突破していく時代なのです。
※橋本淳司著『あなたの街の上下水道が危ない!』(扶桑社)より一部を抜粋して再構成。
(了。第1回から読む)
【プロフィール】
橋本淳司(はしもと・じゅんじ)/水ジャーナリスト。アクアスフィア・水教育研究所代表、武蔵野大学工学部サステナビリティ学科。専門は水資源問題、特に日本における水道事業とその民営化問題について精通している。これまでに多数の書籍を執筆し、新聞やテレビ番組においても水問題の専門家としての見解を発信。地球温暖化や人口減少に伴う水資源の危機に警鐘を鳴らし、さまざまなメディアでの発信や全国での講演活動を行っている。