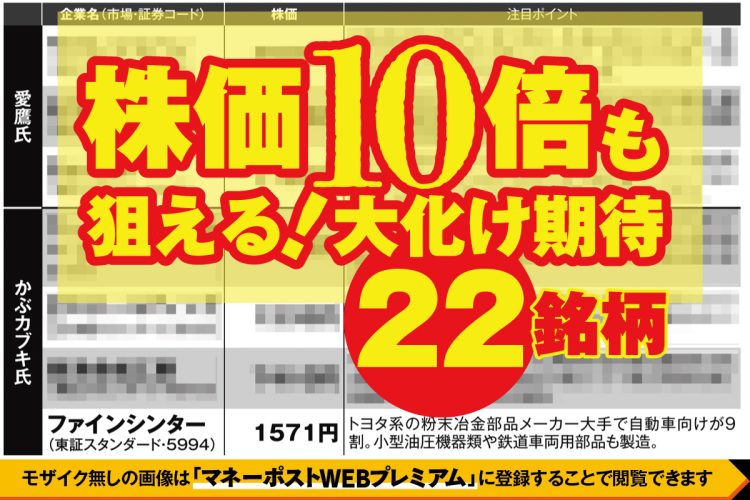今年1月、八潮市で大きく陥没した道路の映像は衝撃を呼んだ(時事通信フォト)
今年1月、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は衝撃をもって受け止められたが、全国に張り巡らされている水道管や下水道管の老朽化は切実な問題となっている。破損リスクの高い箇所を見極め、優先的に対処する「戦略的な更新」が求められるなか、掘らずに管を再生する技術も登場し、維持管理は新たな段階を迎えている――。
今日のインフラ問題を技術と知恵で支える現場の実態を、水ジャーナリスト・橋本淳司氏の著書『あなたの街の上下水道が危ない!』より一部を抜粋して再構成。【全3回の第3回】
劣化予測と更新優先順位の最前線
老朽化が進行する水道管や下水道管を、どの順番で更新していくか──。この問いは、全国の自治体にとって極めて現実的かつ切実な課題です。限られた予算と人員の中で、すべての管路を一度に更新することは不可能です。だからこそ、破損リスクの高い箇所を見極め、優先的に対処する「戦略的な更新」が求められています。
従来は、管の「敷設年数」が主な判断材料でした。年数が経過したものから順に取り替えるというアプローチです。しかし実際には、古くても健全な管もあれば、比較的新しくても急速に劣化するものもあります。こうした違いを生むのは、地盤の特性、地下水の有無、道路の交通量、温度や湿度などの外的要因です。つまり、同じ素材・同じ年数でも、「置かれている環境」によって劣化の進み方は大きく異なるのです。
この現実を踏まえ、近年ではAIや機械学習を活用した劣化予測システムの導入が進んでいます。これらのシステムは、事故履歴や地質情報、管材・口径などの基礎データを統合し、破損の発生確率を算出します。たとえば、「この区域は地盤が軟弱で雨水が滞留しやすい」「この道路は大型車両の通行が多く、振動負荷が大きい」といった情報をAIが分析し、危険度の高いエリアを可視化します。
こうした予測モデルによって、更新の判断基準が大きく変わってきました。敷設年数に依存せず、実際の破損リスクに応じて優先順位を決定する手法が定着しつつあります。健全な古い管はあえて後回しにし、いますぐに対処すべき場所に重点的に投資する──このような判断は、限られた資源の中で最大の効果を得るために不可欠です。
劣化予測の精度が高まれば、突発的な事故の防止にも繋がります。たとえば、破損による断水や道路陥没といった緊急対応が減れば、住民の生活や交通への影響も軽減できます。住民サービスの安定化と自治体の業務効率化を同時に達成する、まさに「予測に基づくマネジメント」の時代が到来しています。
もちろん、AIは万能ではありません。予測に基づく提案を鵜呑みにするのではなく、現場の知見と組み合わせて判断する必要があります。人間の経験と技術、そしてデータに基づく予測の相互補完によって、ようやく的確な意思決定が可能になるのです。