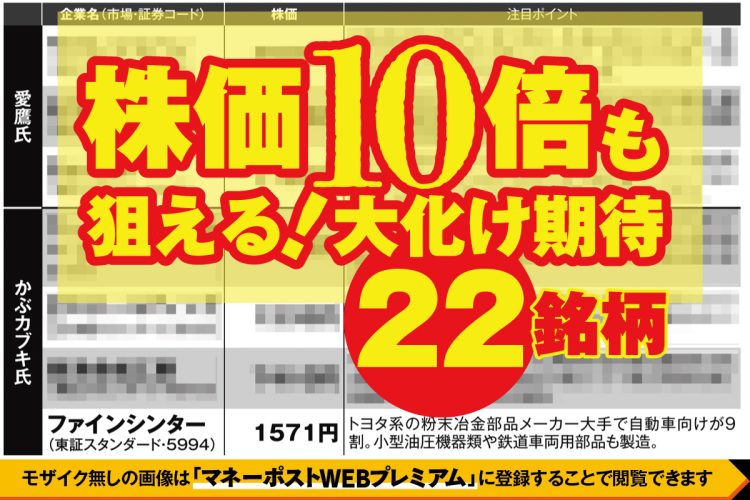総合型選抜の拡大などで多様化する大学入試(イメージ)
大学受験において総合型選抜など推薦入試が主流となってきており、注目度も高まっている。その一方で、一般入試と比べると、推薦入試は対策方法がわかりにくいのが実情だ。一般的に、部活動などの課外活動の実績が推薦入試に求められるという印象を持つ人もいるだろうが、実態はどうか。『大学受験 活動実績はゼロでいい 推薦入試の合格法』が話題の受験ジャーナリスト・杉浦由美子氏がレポートする「課外活動と推薦入試」。【前後編の後編。前編から読む】
* * *
前回記事から「部活など課外活動を頑張ってきた生徒は推薦入試で有利になる」説の真偽を検証している。推薦入試の合格体験記を見ると「部活を続けてきた」とアピールする学生がしばしば出てくる。
前編記事で書いたとおり、老舗の大手推薦塾の合格体験記に登場する男子学生・Aくんも3歳から15年間サッカーを続け、高校では部長として活躍していた。これだけを聞くと部活での活動実績が評価されたように思う。ところがだ。Aくんが合格した上智大学の公募制推薦(総合型選抜と同じように指定校以外の生徒も受験できる推薦入試)は「課外・社会活動の実績はほぼ全く求められない」(塾のサイトより抜粋)というのだ。
では、なぜ、Aくんは上智の推薦入試の受験に成功したのだろうか。
総合型選抜のキモは大学での能動的な学びができること
塾のサイトには上智の公募制推薦で「志望学部の分野への強い関心」が評価されると書かれている。これは具体的に何を問うているのか。
総合型選抜で難関私大に入学したある学生・Bさんはこう話していた。
「大学では自分で決めたテーマについて調べてレポートを書いたり、プレゼンをしたりします。総合型選抜の準備でやっていたことと同じです」
勉強は高校までと大学とでは違う。
高校までの学びは「与えられた課題をこなす」受け身なものだが、大学に入ると自分で問い立てをし、それについて調べてレポートを書くことがメインになっていく。その集大成が卒業論文だ。
そうなると、問い立てを見つける力や先行研究の本や論文を読む力が必要となり、その場合、自発性や能動的に動く姿勢が重要になってくる。
この大学での能動的な学びができることを確認するのが、総合型選抜(公募制)のキモなのである。
このBさんはいわゆる「自称進」(自称進学校)といわれる「部活はほぼ禁止で勉強をさせる高校」、つまり、ただひたすら詰め込み教育をするタイプの学校に通っていた。
部活もほぼ禁止、補講や宿題、小テストなどの詰め込み学習をさせられていた。部活動などの活動実績はゼロだ。暗記が不得意で英語や社会の成績が伸びなかったが、本を読むのが好きで、現国は得意だったために、調べ学習がうまくいき、総合型選抜では“無双状態”。進学した大学以外に、MARCH(明治・青山学院・立教・中央・法政)と成成明学獨国武(成城、成蹊、明治学院、獨協、国学院、武蔵)の一角の総合型選抜にも合格している。
大学では先行研究を探し本や論文を読んで、それを元にレポートを書いていく。これを先取りでやるのが難関大学の総合型選抜なのである。特に上智は高いレベルで「文献を読む力、書く力」を求める。
何年も前から業者が「勉強が苦手な富裕層の子に活動実績を作らせて総合型選抜で大学に進学をさせる」という戦略を打ち立てて、学校や教育産業に営業をしていたが、それがうまくいっていないのは当たり前だ。大学が求めるのは立派なキラキラした活動実績ではなく、「文献を読んで論理的な文章が書けるか」なのだから。