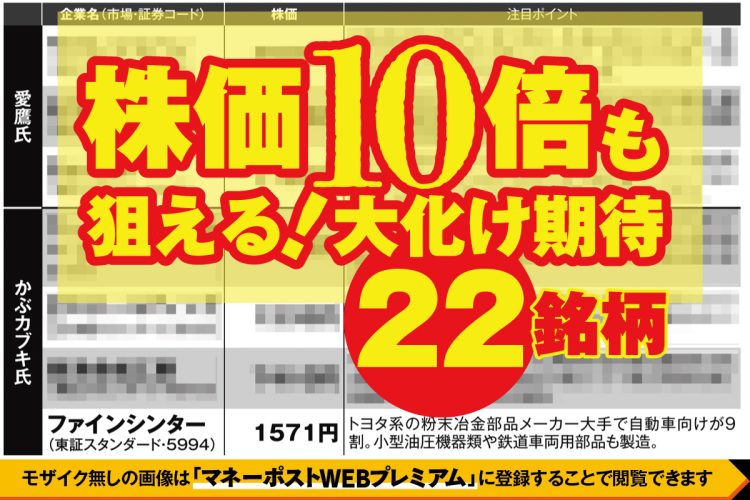SBIホールディングス(HD)の北尾吉孝会長兼社長(写真:時事通信フォト)
SBIホールディングス(8473)は今年に入って相次ぐマーケット注目のニュースや事業展開によって市場評価が一変、株価が上昇基調となり、上場来高値を大きく更新している。今回は、SBIホールディングスのこれまでの注目ニュースや今後の事業展望を踏まえて同社の将来性を、個人投資家、経済アナリストの古賀真人氏が解説する。
* * *
2025年の日本株式市場において、SBIホールディングス(8473)は投資家から熱い注目を集め株価を上昇させている。同社の株価は相次ぐビッグニュースと事業展開により上昇基調に転じ、金融業界の構造変化を象徴する存在となっている。今回は、SBIが注目される背景からマーケットにインパクトを与えた材料、そして今後の成長戦略までを整理していきたい。
SBIホールディングス株は、長年にわたってPBR(株価純資産倍率)0.8倍水準で取引されてきた典型的な割安株であった。しかし、多岐にわたる事業ポートフォリオで、市場の評価は一変している。特に、従来のネット証券事業の安定した収益基盤に加えて、銀行事業や暗号資産事業での新たな収益機会が明確になったことが投資家の期待を高めている。
同社は単なる証券会社ではなく、金融イノベーションを牽引する総合金融グループを目指しており、そこに向けた変化が株価の上昇を牽引している。
また、2025年に入ってからのSBIホールディングスに関するニュースは、好材料が多く、市場も素直に好感していった。最も注目を集めたのは、NTTによる大型出資の発表である。この提携によりSBIの事業展開に新たな可能性が開かれることになった。
SBI新生銀行の公的資金完済も大きなニュースとなった。これは同行の経営正常化を象徴する出来事であり、今後の再上場に向けた道筋を明確にした。投資家にとって、これは将来的なキャピタルゲインの機会を意味する重要な材料となった。
暗号資産事業の拡大も見逃せない要素である。特に、ステーブルコイン事業への参入や暗号資産取引所の機能拡充は、同社の収益多様化戦略のなかで重要な位置づけとなっている。
メディアでの露出機会も増加し、北尾吉孝会長兼社長の発言が市場に与える影響も大きくなっている。特に、北尾氏の「規模の経済性を追求し、SBI新生銀行をコアとする広域地域プラットフォーマーを目指す」という発言のとおり、地銀再編や「第4のメガバンク構想」は着々と進んでいる。地銀全体の1割を占める10行との資本提携を完了していることが、今後の同社の将来性に対する期待を高めている。