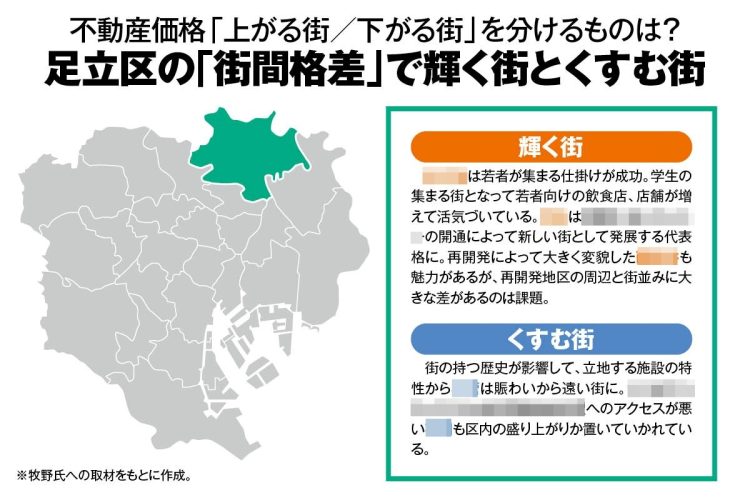プロ経営者には“人知れぬ悩み”があるという(イラスト/井川泰年)
サントリーホールディングスの会長を辞任することになった新浪剛史氏。その経営手腕は様々なメディアから“プロ経営者”と高い評価を受けていた。そうしたプロ経営者について経営コンサルタントの大前研一氏は「社内外から称賛されたまま退任した例は少ない」と指摘する。なぜそうなってしまうのか、プロ経営者はどういった人たちなのか、大前氏が解説する。
* * *
経済同友会の新浪剛史代表幹事が9月30日に辞任した。新浪氏は違法薬物入りサプリメントを入手した麻薬取締法違反の疑いで警察の家宅捜索を受けて同月1日にサントリーホールディングスの会長を辞任し、経済同友会代表幹事の活動を自粛していた。
「私は法を犯しておらず、潔白だと思っている」と新浪氏は述べており、まだ警察が捜査中で真相は不明だが、財界のオピニオンリーダーだった彼の“失脚”は大きな話題になった。
新浪氏は三菱商事から傘下のローソンの社長になり、赤字だった経営を立て直し、日本経済新聞などの経済メディアがたびたび取り上げて“プロ経営者”の評価を得た。その手腕をサントリー創業家の佐治信忠社長(現会長)に買われ、同じ創業家の鳥井信宏氏が社長に育つまでの“中継ぎ役”として社長に迎えられた。
サントリーでは就任10年で売上高を2倍、営業利益を2.5倍にし、佐治氏が買収したアメリカのジム・ビームとサントリーの企業カルチャーをうまく合体させて、海外の売上比率を60%にするという実績を上げた。経済同友会の代表幹事に就任したのは2023年である。
しかし、その後が問題だ。今年3月に鳥井氏が社長に就くと会長になったが、佐治氏とダブル会長という異例の体制だった。本来なら、鳥井氏が社長になった時点でサントリーを辞めねばならなかったはずなのに、引き際を誤ったのだと思う。
なぜ、さっさと辞めなかったのか? これは私の勝手な憶測だが、経済同友会の代表幹事は自分の会社から5~10人ぐらいの社員をスタッフとして連れて行かなければ機能しない。サントリーを辞めたら、そうした人の手配が自由にできなくなってしまうので、居座ったのかもしれない。
過去にも、経営手腕を認められ、他社や他業種のトップを次々に歴任してプロ経営者と呼ばれた人が何人かいる。日本マクドナルドのCEO(最高経営責任者)やベネッセの社長などを務めた原田泳幸氏、日本コカ・コーラや資生堂の社長を務めた魚谷雅彦氏、日本GE(ゼネラル・エレクトリック)やLIXILのCEOを務めた藤森義明氏らだ。外国人では、武田薬品工業のクリストフ・ウェバーCEO、日産自動車のカルロス・ゴーン元CEO、オリンパスのシュテファン・カウフマン元CEOなどである。
これらの名を挙げてみると、プロ経営者と言われる人物で社内外から称賛されたまま退任した例は少ない。
たとえば、原田氏は日本マクドナルド創業者の藤田田氏の影響力を排除し、当初はアメリカ式の改革を進めて成果を収めたが、結局、大赤字を出して退任した。藤田氏が逝去した時は社葬を執り行なわなかったので、藤田氏と親しく「ドナルド・マクドナルド・ハウス財団」の理事でもあった私は悲憤慷慨したものである。
魚谷氏も同様だ。資生堂は中国やアメリカなどの海外事業にことごとく失敗して未曾有の業績不振に陥り、魚谷氏はその責任を取るかたちで昨年末にCEOを退任してシニアアドバイザーになった。ところが、7月に日本経済新聞に掲載された「私の履歴書」は自画自賛のオンパレードで、業績悪化は新型コロナ禍などの外的な要因に帰している。
外国人の場合も、ゴーン氏の末路は周知の通りだし、カウフマン氏は違法薬物問題で辞任して麻薬特例法違反で有罪判決を受けた。