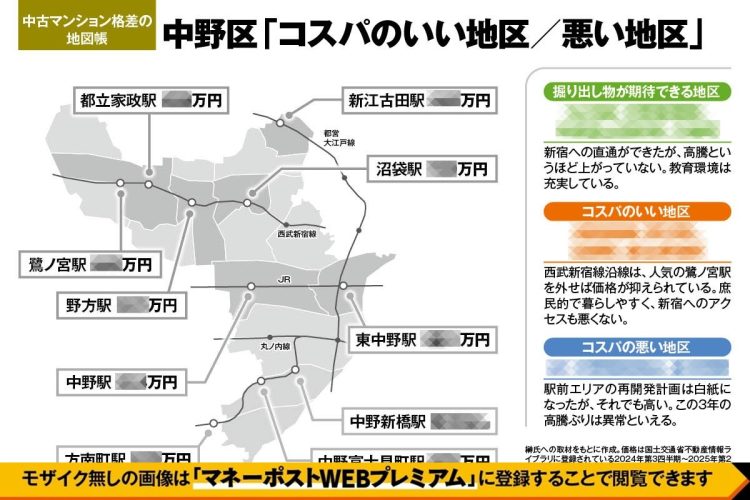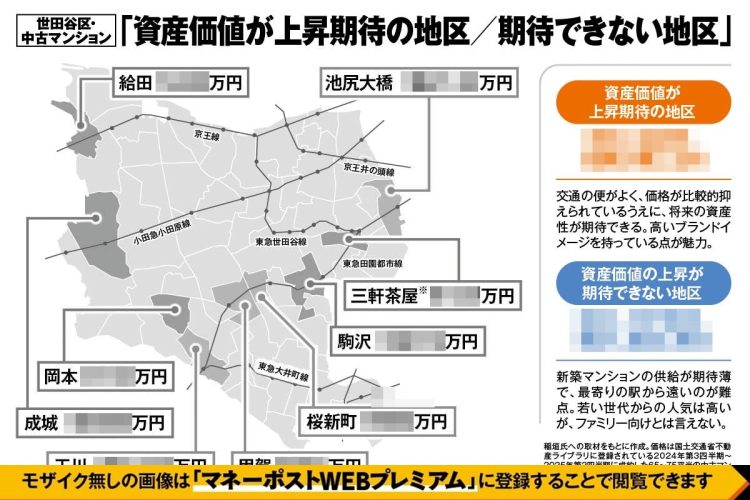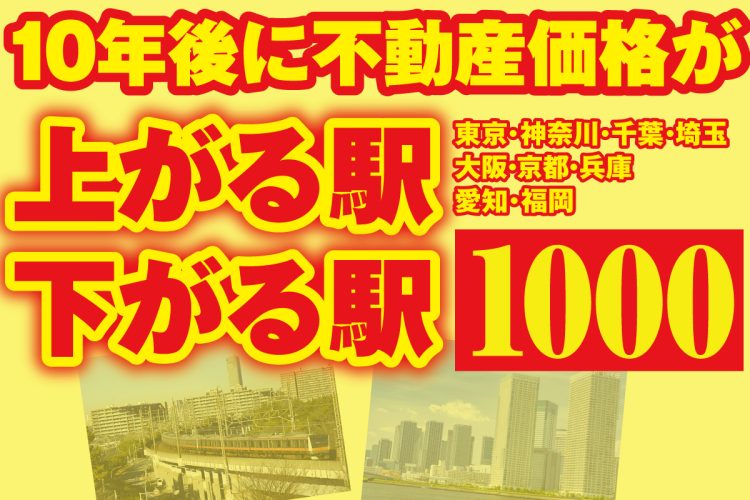慶応義塾大学ほか、人気大学の2026年入試の傾向はどうなるのか
2025年の津田塾大学の情報科学科の入学者数が定員を下回ったことが話題となった。受験や教育について取材するノンフィクションライター・杉浦由美子氏によれば、「大学の定員充足率の影響もあるのではないか。人気の大学は、定員充足率を抑えるために合格者数を絞ることも起きてくる」と指摘する(関連記事参照)。では、どのような大学が今後、合格者数を絞ると予想されるのか。『大学受験 活動実績はゼロでいい 推薦入試の合格法』が話題の杉浦由美子氏が、定員充足率を踏まえて、2026年入試で「難化する大学」「易化する大学」について考察する。
■関連記事を読む:津田塾大・情報科学科の“定員割れ”は何を意味するのか? 補助金に影響する「定員充足率」がその年の入試難易度を左右しかねない現実