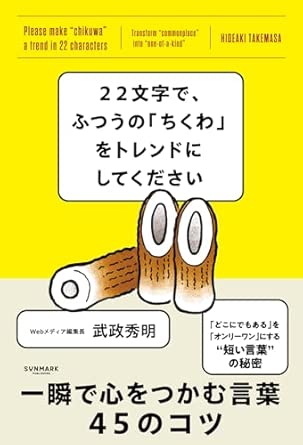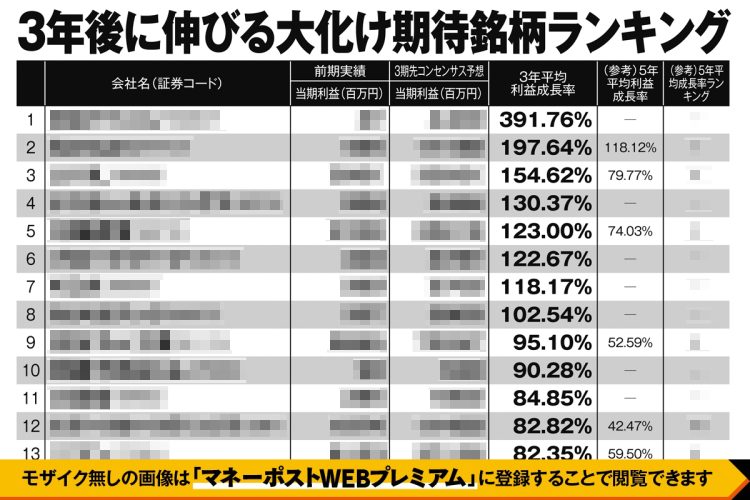相手の「知っていること」と並べる
私たちは、何かと比較して、新しいことを理解することがあります。
「サブスクって何?」
「新聞の定期購読と同じ仕組みで、月額制の会員サービスのこと」
「セイコーマートって何の企業?」
「北海道ではセブン-イレブンと同じくらい有名なコンビニだよ」
すでに知っているものの上に、新しいものを重ねると、概要がざっくり理解できます。
こうした方法が効果的な理由は、相手の既存の知識や体験を活用できるからです。だからこそ相手は実感を持って、理解できるのです。
知名度の高い固有名詞を「てこ」にする
ちょっと専門的になりますが、ウェブの記事では、この仕組みを使って、「知名度の格差を逆手に取る」こともあります。
以前、茨城県ではナンバー1を誇るサザコーヒーの記事タイトルを考案した時の話です。
当初私は、「サザコーヒーが茨城でナンバー1を続けられる理由」というタイトルを考えました。しかし、サザコーヒーは、茨城県ではナンバー1でも、ほかの地域の人にはそのすごさを、すんなりとわかってもらえません。
どうしたら全国の人に「サザコーヒー」のすごさをわかってもらえるのか。
そこで、次のようなタイトルにしました。
「茨城でスタバとコメダを圧倒する名店の正体(*1)」
【*1】高井尚之「茨城でスタバとコメダを圧倒する名店の正体」東洋経済オンライン(2017年11月19日)
誰もが知っている大手ブランドと並べることで、読む人に、「圧倒するってどんなすごいお店なんだろう」と、その意外性に興味を持ってもらう狙いでした。
あまり知られていない物事であっても、全国的に有名なものを「踏み台」にして、関心を持ってもらうことができたのです。
同じ原理で、抽象的なテーマも身近な固有名詞で表現できます。
[抽象]物価上昇のあおりを喰らい始めた外食業界の苦悩
[固有名詞]マクドナルドの値上げに驚いた人が知らない真実(*2)
【*2】坂口孝則「マクドナルドの値上げに驚いた人が知らない真実」東洋経済オンライン(2023年1月8日)
前者は「物価上昇」「外食業界」といった抽象的な表現で距離感がありますが、後者は読者の実体験(マクドナルドの値上げに驚いた)から入ることで、同じテーマをより身近に感じさせています。「マクドナルド」という誰もが知っている具体的な店名が、抽象的な「外食業界の苦悩」を自分ごとに変えているのです。
逆にいえば、相手の知らない固有名詞を「最初の言葉」に入れた時点で、スルーされてしまう確率が高まります。知らないものに対しては、人は関心を持ちづらい。しかし、全国的に有名なものを「踏み台」にして、あまり知られていない対象への関心を押し上げることができます。
※武政秀明・著『22文字で、ふつうの「ちくわ」をトレンドにしてください』(サンマーク出版)より一部抜粋して再構成
『22文字で、ふつうの「ちくわ」をトレンドにしてください』著者の武政秀明氏
【プロフィール】
武政秀明(たけまさ・ひであき)/Webメディア編集長。1976年兵庫県神戸市生まれ。1998年関西大学総合情報学部卒。自動車セールスパーソン、新聞記者を経て、2005年東洋経済新報社に入社。2010年から東洋経済オンライン編集部。副編集長、編集長、編集部長を歴任。約12年間の在籍中に自身で7000本超のタイトルを考案してヒット記事を連発する一方、同期間にサイト全体で数万本に及んだ記事のアクセス傾向を徹底的に研究。読者の関心を大きく左右する記事タイトル=最初の言葉の作り方を独自に体系化する。東洋経済オンライン編集長時代の2020年5月には過去最高となる月間3億457万PVを記録。2023年5月にサンマーク出版へ転職後、SUNMARK WEBを立ち上げて編集長を務める。