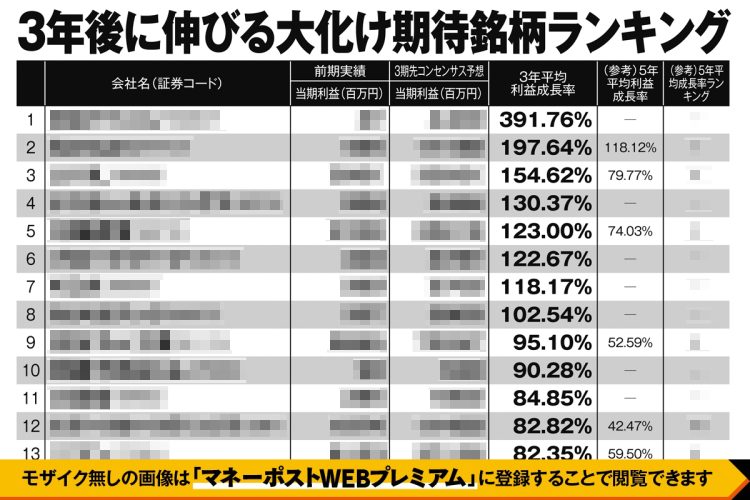*17:04JST 日本金属:今期黒字転換見通し、PBR0.2倍台で推移する金属加工メーカー
日本金属<5491>は1930年創業のみがき帯鋼事業と加工品事業を手掛けるメーカーである。みがき帯鋼事業の主要製品は冷間圧延ステンレス鋼帯、みがき特殊帯鋼、マグネシウム合金帯、極薄電磁鋼帯である。加工品事業の主要製品はファイン・プロファイル(精密異形圧延製品)、型鋼製品、ファインパイプ(溶接引抜管)などである。2026年3月期第2四半期(累計)の売上高構成比は、みがき帯鋼事業82.9%、加工品事業17.1%。
同社の強みは、長年培ってきた生産技術と設備力となる。冷間圧延ステンレス鋼帯においては高い表面品質が求められる高級車用外装モール用材や、600ミリの広幅で板厚0.1ミリ未満の箔の生産は競合が限られる分野であり、安定した品質と量産力を併せ持っている。また、マグネシウム合金帯や板厚0.1ミリ未満の極薄電磁鋼帯における世界有数のメーカーであり、マグネシウム合金帯はモバイル機器などに、極薄電磁鋼帯はHVDC(高電圧直流送電)向けに使用されている。ファイン・プロファイルはフォーミング加工とのハイブリッド加工で直動機器に採用されている。ファインパイプにおいては医療・分析機器向けのニーズを取り込んだ内面高精度管やFINE PEEK-ST(ステンレス鋼とPEEK樹脂の複合管)といった特殊製品においても高い精度を実現している。競合は中国や台湾メーカーなど海外メーカーが存在するが、同社は品質・技術面で優位性を維持している。
2026年3月期第2四半期(累計)の連結業績は、売上高24,294百万円(前年同期比5.8%減)、営業損益320百万円の黒字に転換した。みがき帯鋼事業では、電池用途や精密ベアリング用途、精密機械用途などの需要が回復したが、主力製品である自動車関連用途では、中国向けの光モール用途が低迷したことで売上高は微減収となった。加工品事業においても、岐阜工場取扱製品にて内面高精度管や文具関連用途などが回復したが、福島工場取扱製品にて主力製品であった自動車駆動部品用高精度異形鋼が自動車電動化の影響を受けた需要家の購買方針により2025年3月期の契約で終息して減収に。ただ、両事業ともに高収益品の増販、生産効率の改善、販売価格の是正などにより大幅増益を確保した。
今期の連結業績見通しは、売上高53,400百万円(前期比4.1%増)、営業損益900百万円の黒字を見込んでいる。国内サプライチェーン間での自動車部品の在庫調整が進展することで需要の回復が見込まれ、原材料などの諸コスト上昇等を反映した販売価格の是正の効果が発揮されるのが、下期にずれ込むものとの予想から第2四半期(累計)は損益が均衡するに留まるものの、通期では黒字化を見通している。
中長期戦略では、2030年3月期に売上高650億円、経常利益50億円の達成を目標としている。創立100周年にあたる2030年に向けて、同社の原点である圧延技術と加工技術を極め、圧倒的な差別化を実現する製品の開発、事業化を進めていくようだ。成長ドライバーとして掲げるのは、既存事業の変革と新規事業となる。既存事業の変革においては、表面厳格・形状厳格など、既存技術を深化することで機能を充実させ競争力を高めたファインブラック(黒加飾ステンレス鋼)などを拡大する。一方、新規事業では、次世代電池、新エネルギー車、医療産業機器などをターゲット分野として、マグネシウム合金は常温加工の課題克服を目指した研究開発を進めており、軽量・高強度材料として次世代電池や自動車用途での採用が期待される。極薄電磁鋼帯についてはモーター用途で産業用ドローン向け需要を見込み、ファイン・プロファイルはアルミや銅などの非鉄金属を原料とした製品で新規分野を開拓する取り組みが進んでいる。また、2025年4月にプロダクションプロセス・サポート部を新設し、刻々と変化する市場ニーズに対して、圧延・成形加工・溶接引抜管の設備・技術・機能を活用し、あらゆる開発・試作ニーズに応えていくことでビジネスチャンスの拡大を目指していくようだ。
株主還元については、配当性向20%を目安に掲げているが、直近は業績の悪化や成長分野への投資を優先したことなどから無配を継続。黒字転換の定着が確認できれば復配を検討する方針で、2025年11月4日に自社株買いを実施するなど、柔軟な株主還元政策も視野に入れている。一方でPBRは1倍を大幅に割れて推移しており、低評価の改善には収益基盤の安定化と新規事業の進捗が不可欠となる。IR方針としては、まずは個人投資家層の拡大に注力することで流動性を高め、機関投資家からの投資対象となるよう取り組んでいる今期利益回復局面に入る想定だが、PBR1倍割れ改善に向けての収益性改善と認知度向上に注目しておきたい。
<FA>