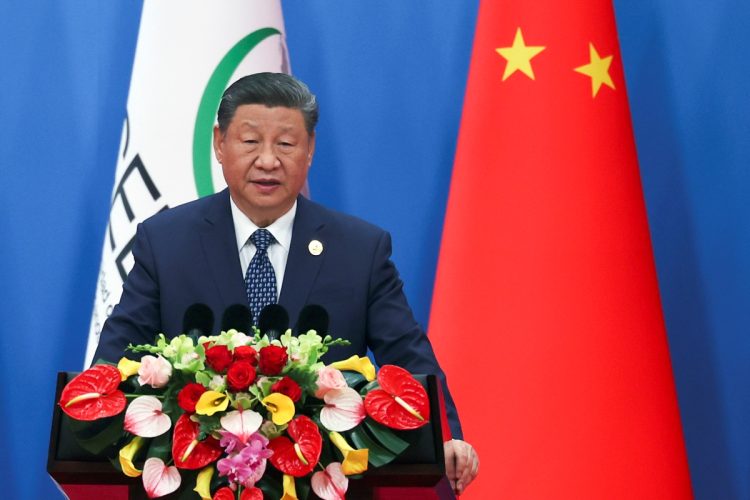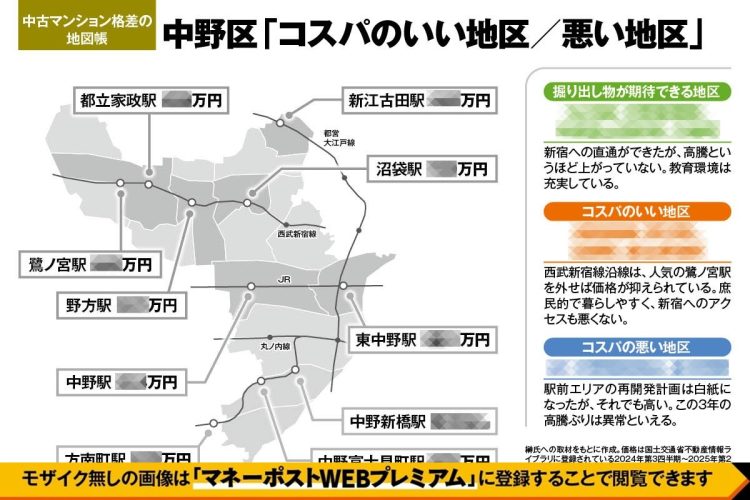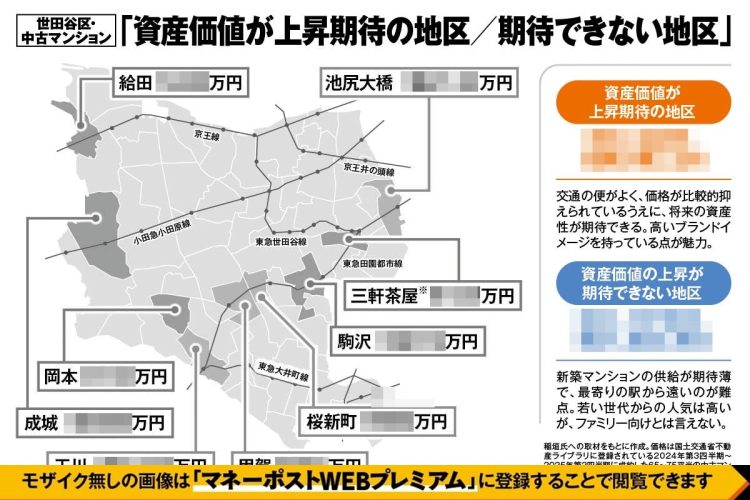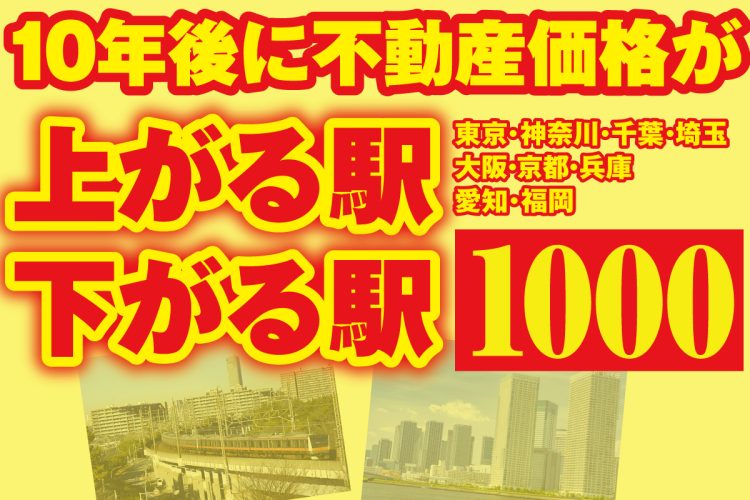着々と経済圏を拡大させている(習近平国家主席。Getty Images)
6月30日にはS&P500、NASDAQが過去最高値を更新するなど、グローバル投資家はリスクオン姿勢を強めているが、中国株にも強気の見通しを持つ投資家が増えてきた。ハンセン指数は足元ではわずかに調整しているが、それでも、トランプ相互関税政策の悪影響を既に織り込み、6月30日の終値は2万4072ポイントで、3月19日に記録した約3年1カ月ぶりとなった高値まであと3.3%の水準まで上昇している。
上昇要因として、中東情勢の緊張緩和、米国のインフレ懸念の後退と利下げ期待の高まりなどといったグローバル要因に加え、「トランプ相互関税による中国経済への影響は意外に小さい」といった中国特有の要因が指摘されよう。
合成麻薬の原材料となるフェンタニルの国内への違法な流入を理由に、米国は中国に対して2月4日から原則として全品目に対して10%の追加関税を賦課したが、その後中国が報復措置をとったとして3月4日には関税率を20%に引き上げた。4月2日、トランプ政権は相互関税措置を発表、中国に対する関税率を34%としたが、この際も中国が報復措置をとったことで短期間に大幅な引き上げが行われ、10日には125%となった。もっとも、その後は5月12日に実施された米中閣僚会議によって10%に引き下げられている(ただし、24%相当は90日間の停止、フェンタニル流入などを理由とした20%は継続)。追加関税率があわただしく変動する中で、5月の輸出への影響が心配されたのだが、前月の8.1%増(ドルベース、以下同様)からは鈍化したものの、それでも4.8%増の伸びを確保している。
もちろん、米国向けは34.6%減(海関総署データから推計)と大幅に減少している。しかし、他国の増加分が米国向け減少分を上回っている。米国の減少額を100として主な地域別の増加額を比べると、ASEAN諸国が50、EUが34、アフリカが32である。これらの地域向け輸出の伸び率を示すと、ASEAN諸国が15.0%、EUが11.9%、アフリカが33.4%で、アフリカを除けば極端な増加率ではない。貿易先の多角化加速で何とか乗り切っているようにみえる。
第一次トランプ政権が対中追加関税を賦課し始める前の2017年における米国向け輸出シェアは19%で最大、EUは16%、ASEAN諸国は12%、南米は6%、アフリカは4%であった。それが2024年には15%まで低下、EU(14%)よりは大きいものの、ASEAN諸国(16%)とは順位が逆転していた。さらに、相互関税賦課の結果、5月の米国向け輸出シェアは9%まで落ち込んでおり、ASEAN諸国の18%、EUの16%を大きく下回っている。ちなみに、アフリカは6%までシェアを上げており、米国との差は3ポイントに迫っている。
もはや、米国が自国市場の大きさを武器に関税を使って譲歩を迫るやり方は、中国に対しては有効ではなくなったようだ。
輸入に関しては、相互関税政策による米国シェアの目立った低下は見られないものの、2024年の統計において米国のシェアは6%に過ぎず、ASEAN諸国15%、EU10%、南米9%よりはるかに低く、台湾8%、韓国7%をも下回る。