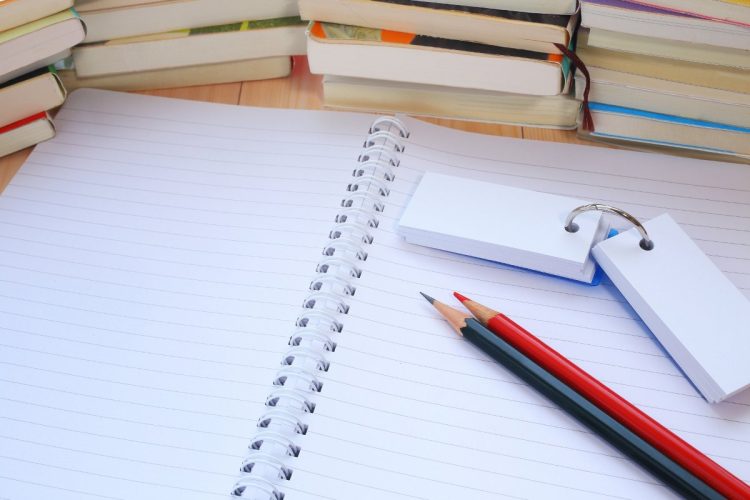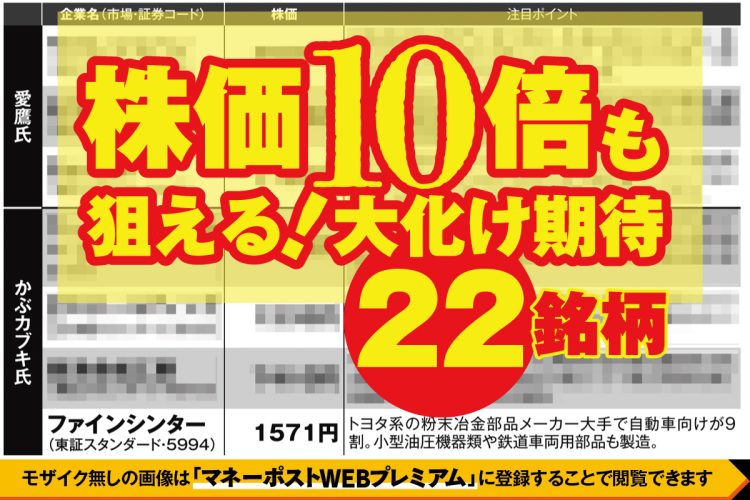推薦入試に求められている能力は?
大学入試の大半が総合型選抜など推薦入試となっている昨今。推薦入試の対策を謳ったビジネスも拡大しているという。その内実はどういったものか。『大学受験 活動実績はゼロでいい 推薦入試の合格法』が話題のノンフィクションライター・杉浦由美子氏がレポートする。【前後編の前編】
* * *
大学入試の半分が推薦入試になってきている。こうなっていくことは10年前から予想されてきたことだ。その「推薦拡大」の流れの中で、一部の業者やNPOなどはこうセールストークを繰り広げていた。
「これからは推薦入試が主流になります。そこには一般選抜とは違う市場があります。勉強が苦手な子でも活動実績を作れば、大学に行けるようになります」
彼らはこうもいう。
「推薦入試が拡大するのは今までの詰め込み教育ではダメだと分かったからです。コミュニケーション能力などの非認知能力を伸ばさないと、日本の失われた30年を取り戻せません。ですから大学は学力以外の部分を評価する入試を拡大するのです。就職の採用でもコミュニケーション能力が高い学生を求めています」
この“もっともらしい”セールストークを真に受けた教育産業や高校が「キラキラした探究学習をさせ、活動実績を作って、大学に進学させよう」という試みを始めた。中には学校をひとつ作ってしまったほどだ。
立派な設備を揃えた理科実験室でインスタ映えするような実験をさせたり、海外研修で現地の投資家の前でプレゼンをさせたりもした。こういった体験をアピールして総合型選抜で早慶上智やICU、MARCHなどの難関大学に進学させようという試みだ。
しかし、そういう試みに取り組んだ高校の合格実績を見る限り、正直、結果が出ていない。そもそも早慶上智などの総合型選抜の合格者には難関高校出身者も多く、「学力が高い生徒」が受かりやすい入試なのだ。
また、ある中堅高校でも、「著しい活動実績がある生徒」が慶應やMARCHの総合型選抜に全敗し、一方で、同じ高校の特進クラスの生徒が慶應とMARCHの総合型選抜3つに合格したというケースもある。前者が探究学習で大きな成果を作った一方で、後者は3年間、ただひたすら勉強をさせられたのにだ。
不思議なのは、多額のお金を投入して「活動実績を作らせて総合型選抜で大学に進学させようとする学校」を作る前に、なぜ難関私大の総合型選抜の「中身」を調べないのか、ということだ。