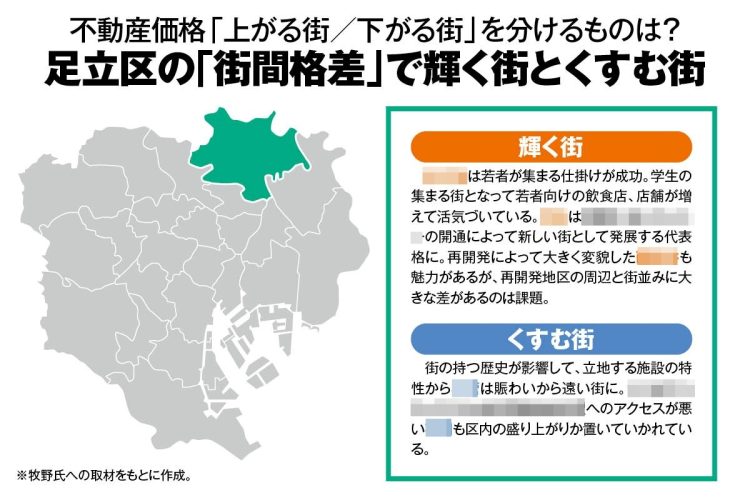受験生と保護者にとって“勝負の夏”が来た。受験する中高一貫校や高校を選ぶ際の指標として、その学校の「大学合格実績」に注目する人は多いだろう。ただ、各学校が公開する資料にも同様のデータは掲載されているが、「実際の進学者数」について詳しく紹介されるケースは少ない。合格実績の場合、一人の生徒が複数の大学に合格すればそれらをすべてカウントするのが一般的だ。一方、進学実績がわかればその高校全体としての“真の実力”がわかるのではないか──。
今回、マネーポストWEBは「大学通信」の協力を得て、全国約2100校分の2025年現役進学実績を集計した。ここでは旧帝大(東京大学、京都大学、北海道大学、東北大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学)と一橋大学、東京科学大学の国立大9校と、早慶上理の難関私立大への進学者数を合わせ、ランキング形式で紹介する。難関国立大と私立大への進学者数を合計すると、既存の「合格数ランキング」とは違った景色が見えてきた。(取材・文/清水典之)
目次
合格者数より「進学者数」を重視すべき理由
受験情報を扱うメディアが毎年恒例のように取り上げる「東大合格者数ランキング」や「早慶MARCH合格者数ランキング」。中学受験や高校受験の受験生やその親は、そうしたランキングを学校選びの参考にすることが多い。
しかし、受験する学校選びで、より参考になるのは合格者数より進学者数ではないか。『受験天才列伝──日本の受験はどこから来てどこへ行くのか』(星海社新書)の著者で、Xアカウント「じゅそうけん」で11万人のフォロワーをもつ伊藤滉一郎氏は、進学者数という数字の信頼性についてこう説明する。
「たとえば、1人の生徒が早稲田の3学部に受かったとすると、高校側は早稲田の合格者数を“3”とカウントするのが一般的です。首都圏の私立中堅高のなかには、高1の段階で私大専願に絞って3年間3科目を集中的に勉強するよう指導して、早慶上理、MARCHなど私大の合格者数を“稼ぐ”学校があります。つまり、合格者数は学校の進路指導の方針によって大きく左右されるということです。しかし、進学者数で見れば、生徒1人が進学する大学は1校。その学校でどのくらいの人数が難関大に進学できたかが一目瞭然です」
たとえば、ある首都圏の高校の進学実績を検討すると、ある年、MARCH合格者は約300人だったが、実際に進学したのは40人だった。同じ年、旧帝大+東京科学+一橋に60人、早慶上理に100人、医学部に10人が進学している。それらの進学者数を合計すると210人となる。約300人いるMARCH合格者内で相当数の重複が起きていることがわかるだろう。
「MARCH合格者数300人」とだけ聞けば、その学校で300位以内の成績を保持すれば合格の可能性があるように錯覚しがちだが、実際の進学実績に着目すると、同じ考え方でMARCH以上の現役合格が期待できるのは、「210位以内」の成績がラインとなる。もちろん、これはあくまで目安だが、延べ人数である合格者数よりも信頼性が高いことは言うまでもない。同時に、難関大の進学者数は、その学校の進路指導の実力をはかる目安にもなる。
進学者数という数字が非常に重要にもかかわらず、合格者数のランキングばかり目にするのは、ほとんどの高校が公式サイトやパンフレットなどで進学者数を公表していないからである。首都圏で、合格者数・進学者数ともに公開している高校は、開成と筑波大附属駒場。武蔵(私立)は進学者数のみ公表しているが、これらの高校以外で進学者数を公表している高校はまれであろう。
難関大合格者ランキングとはひと味違ったランキングに
では、全国の中高一貫校や高校で、旧帝大や早慶上理などの難関大学に現役進学した生徒が多い学校はどこか。毎年、全国約4300校の高校へアンケート調査を実施する「大学通信」の協力を得て、『2025年 難関大「現役進学者数」全国ランキング』を作成して公開する。
本記事では、日本の難関大(東大・京大を含む旧帝大と東京科学大、一橋大、早大、慶大、上智大、東京理科大)への「進学者数」を高校別に合計して、多い順にランキングした(別掲の表を参照。一部の大学附属校を除く。また、昨今、大学入試においては実質的に現役生だけが対象になる総合型選抜や学校推薦型選抜による入学が全体の半数以上に増えている。そうした傾向を考慮して、進学指導における“高校の実力”にフォーカスするため、現役進学者のみをカウント対象にした)。
結果を見ると、受験シーズン後にメディア等で見かけた難関大合格者ランキングとはひと味違った、非常に興味深い顔ぶれとなった。1位に輝いたのは、名門進学校として知られる開成でも日比谷でもなく、他県の公立高校なのである。
【次項から、難関13大学について、高校別に2025年の現役進学者数が多かった順に上位102校をランキング形式で一覧表に示している】