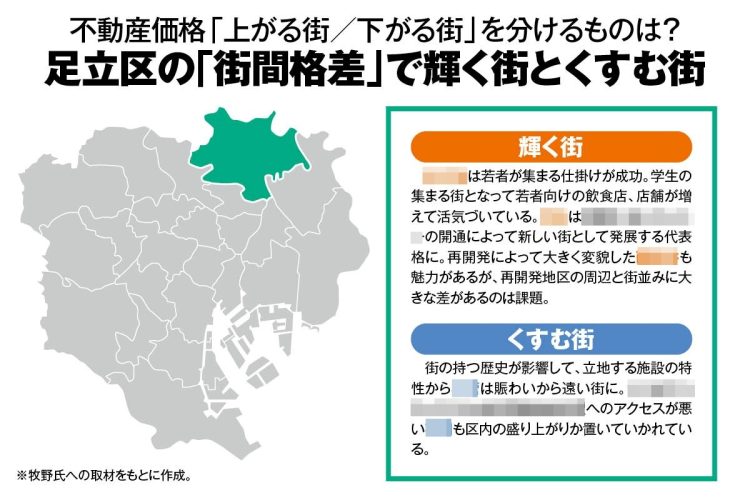N高とR高の校長を務める奥平博一氏にインタビュー
近年、「通信制高校」の生徒数増加が話題だ。かつては何らかの事情で通学できない人や、働きながら高卒資格を得ようとする人などに利用される面が大きかったが、現在では中学卒業後の進路として選んだり、全日制や定時制高校から転入・編入したりするケースがほとんどだという。「不登校の受け皿」としての側面が語られることがあるが、実際はどうなのか。その他の高校とは何が違うのか。私立の「通信制高校」として2016年に開校して以来、全国から生徒が集まるN高等学校の奥平博一校長に、フリーライターの清水典之氏が聞いた。
目次
日本の通信制高校の生徒の1割超が在籍
N高、S高、R高……。知らない人が聞けば、どこかの学校のイニシャル表記かと勘違いするかもしれない。さらに、これらの学校から東大7人、旧帝大23人、早慶に82人の合格者が出て、海外大にも203人が進学している(2024年度)と聞けば、どんな進学校かと思うが、実は3万2000人もの生徒が在籍する通信制高校の名前である。
近年、通信制高校に進学する生徒が増加している。文科省の「学校基本調査(2024年度)」をもとにリクルート進学総研が集計したデータによると、2024年度の通信制高校在籍生徒数は29万87人で過去最高となり、10年前の2015年度と比較すると、約1.6倍に増加した。全日制、定時制、通信制を合わせた生徒数は約320万人なので、いまや11人に1人が通信制高校に在籍していることになる。学校数も2024年度に初めて300校を超え、公立79校、私立224校となった。
この303校の中で、もっとも在籍生徒数が多いのが、学校法人角川ドワンゴ学園が運営するN高等学校・S高等学校・R高等学校(2025年4月開校)である。N高校が開校した直後の2016年5月、生徒数は1570名だったが、9年後の2025年3月末時点でN高・S高の合計で3万2613名と、20倍以上に膨れあがっている。日本の通信制高校の生徒29万人中、実に1割超となる3万2000人がN高グループに在籍しているわけで、今や通信制高校の代表的存在と言える。
なぜこの学校にこれほど多くの生徒が集まってくるのか。N高・R高の奥平博一校長に、この学校に関する詳細を尋ねた。
「学校名に意味をもたさない」との理由から名付けられた
まず、誰もが気になるであろう、校名の由来について聞くと、こう答えた。
「当学園の理事を務めている川上量生(KADOKAWA取締役)の発想で、“学校名に意味をもたさない”という理由からです。学校名を聞いて、“ニコニコ動画”のNとか、“ニュー”とか、いろんな意味を想像されるのですが、我々としては特に定義をしていません。
S高を作るときも、もし“N第2高校”とすると、N高が本校で、二番手のように受け取られかねないので、S高としました。R高も同様です。N高の開校時、本校を設置する沖縄県庁へ申請書を出しに行ったとき、担当職員はN高校という名前を見て、『ああ、まだ学校名が決まっていないんですね』と言いました。『いえ、これが学校名です』と答えたら、30秒くらいの沈黙の後、『まあ、いいんですけどね……』と(笑)」(奥平校長・以下同)
学校名に意味をもたさないとのことだが、では、N高、S高、R高の違いは何か。
「N高の定員は、申請時に2万人としたため、生徒数がそれを超えそうになったので2021年4月にS高を開校したという経緯です。今後、さらに4万人を超える可能性があるので、2025年4月にR高を開校しました。
基本的にカリキュラムや学費、全国に約100箇所ある通学コースのキャンパスなどは3校とも共通で、唯一の違いは本校の場所です。N高は沖縄県うるま市、S高は茨城県つくば市、R高は群馬県桐生市に本校があり、2年次に1回、本校での必修スクーリングがあるので、(入学希望者は)本校所在地で選んでもらえばいいと思います」
教育課程の中身は基本、3校とも共通なので、沖縄旅行に行くつもりでN高を選ぶとか、家から近いのでS高を選ぶとか、そういった基準で選べばいいという。