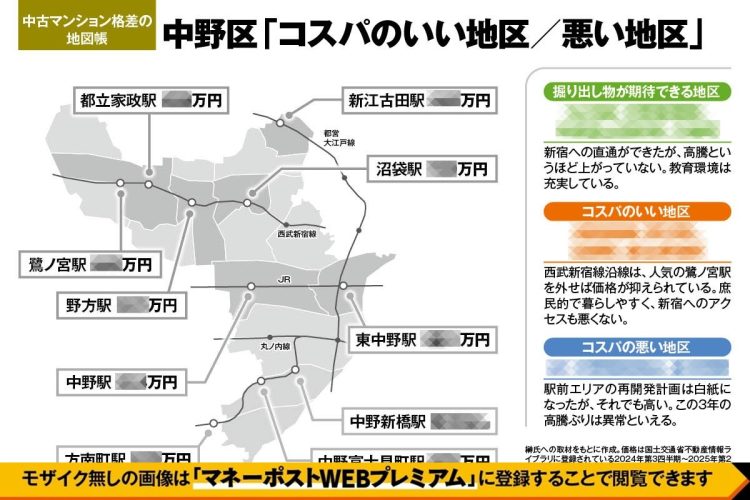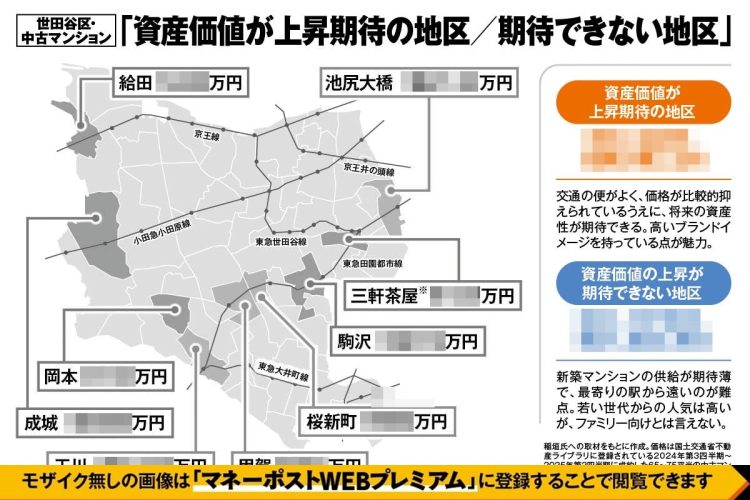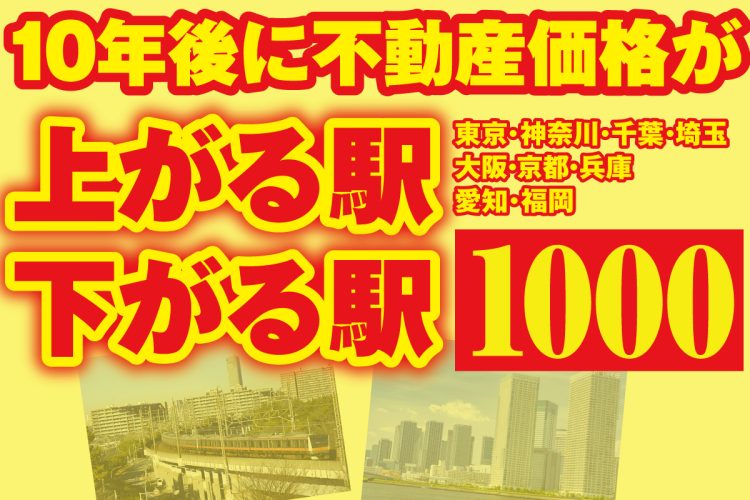2002年にノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊氏(左)と化学賞を受賞した田中耕一氏はともに「公立高校」出身(AFP=時事)
中学受験や高校受験の際に志望校選びの基準となるのが「大学進学実績」だ。マネーポストWEBは「大学通信」の協力を得て、全国約2100校分の2025年の現役進学者数を集計。シリーズ第1回記事では「旧帝大+東京科学大+一橋大+早慶上理」への進学者数を取り上げ、延べ合格数と比較する形で高校別に全国ランキングを作成・公開した。
今回はその番外編として、「ノーベル賞受賞者」を輩出した高校の現在地を検証する。日本が誇る知性は、どのような高校で学び、その素地を育んだのか。フリーライターの清水典之氏がレポートする。
>プレミアム登録して「ノーベル賞受賞者の出身高校の今」を見る【初回登録月は無料】
「東京の高校」出身のノーベル賞受賞者はただ1人
日本出身(外地を除く)のノーベル賞受賞者(個人)は文学賞や平和賞も合せて28人。東大と京大の出身者が多いことは知られているが、「出身高校」となると、地元以外にはあまり知られていないのではないか。調べてみると、実はほとんどの受賞者が、地方の公立(国立)高校出身であった。
東京の高校出身でノーベル賞を受賞したのは、日比谷高校卒の利根川進氏(生理学・医学賞、1987年)ただ1人。私立高校出身の受賞者もまれで、旧制同志社中学校(現・同志社中学校・高等学校)を経て旧制三高を卒業した江崎玲於奈氏(物理学賞、1973年)と、灘中・高卒の野依良治氏(化学賞、2001年)の2人だけである。
日本の人口の約10%が集中し、平均所得も高く、教育熱も高いとされる東京(の高校)から、なぜ利根川氏以外のノーベル賞受賞者が輩出されなかったのか。
『「中学受験」をするか迷ったら最初に知ってほしいこと』(Gakken)著者で、Xアカウント「東京高校受験主義」で5万4000人のフォロワーをもつ塾講師の東田高志氏は、「あくまで個人的な意見」と前置きしつつこう答える。
「利根川進氏は愛知県出身。小・中を富山県や愛媛県などの地方で過ごし、東京に引っ越して日比谷に進学しています。だから、本当の意味で東京出身のノーベル賞受賞者は1人もいないと言えるかもしれません。
東京の教育は、効率性を追いすぎるきらいがあると思います。子供が好きなことをして遊んでいるのを“時間の無駄”と切り捨て、詰め込もうとするようなイメージです。人口が多くて競争が激しいので、できるだけ効率的なカリキュラムで最短距離を走らせようとする。子供を放置しないんです。
たとえば、大谷翔平さんが東京で生まれていたら、今の活躍があったかどうか。彼の発言や行動を見ていると、とても頭がいい人であることがわかるので、“この子は勉強できそうだから”と小学4年で中学受験塾に入れて、野球は趣味的に続けるだけになったかもしれない。そうなると効率的に考えて、“医学部に入って医者になるのが現実的な成功者への道”という結論になりがちです。そういった価値観に染まりにくいのが、地方のいいところです。本人が好きなことを好きなだけやらせないと、圧倒的な才能は伸びてこないと思います」
東京の場合、手っ取り早くわかりやすい目標にルート設定して子供を走らせてしまうという“落とし穴”にはまりがちだという。地方に比べて情報と機会が溢れている東京だからこそ、逆にそうなるのかもしれない。
とはいえ、ノーベル賞を受賞した俊英たちは、軒並み東大・京大など難関大に合格できるだけの学力を備えていたのは事実である。では、こうした人材を輩出してきた地方の高校は、今どんな姿になっているのか。