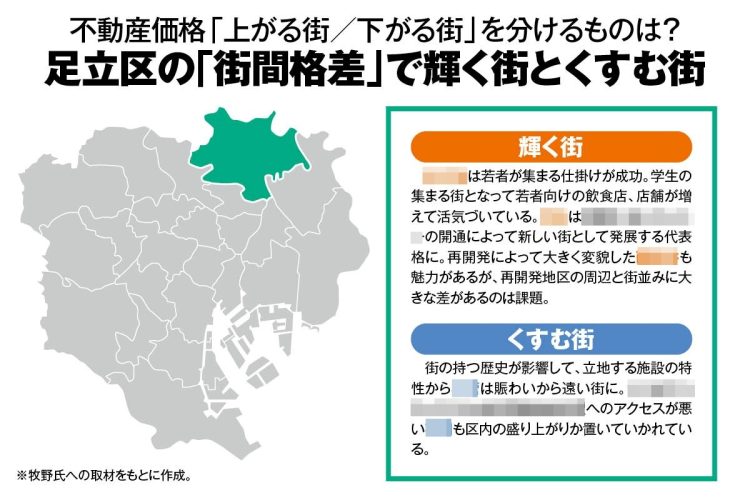核融合エネルギー開発は高市早苗新政権の誕生で注目される分野の一つだ
高市早苗首相が経済政策の柱として掲げているのが、エネルギー安全保障の軸となる「核融合エネルギー」の実現だ。現在の日本の状況は。その政策で影響を受けるのはどういった企業なのか。個人投資家、経済アナリストの古賀真人氏が分析し、解説する。
高市政権で加速が期待される「核融合エネルギー」実用化
日本初となる女性総理として、高市新総理が誕生した。高市氏が掲げる「責任ある積極財政」は、単なる景気刺激ではなく、AI・半導体・データセンターなどの次世代産業を支えるための“成長型財政政策”だ。その柱のひとつに据えられているのが、エネルギー安全保障の軸となる「核融合エネルギー」の実用化である。
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは出力が不安定で、火力発電はCO2排出を避けられず、原発は放射性廃棄物や安全性の問題がつきまとう。つまり、「安全性」「環境負荷」「安定供給」という3つの課題を同時に満たす電源が存在しないのが、日本を含む世界のエネルギー構造の課題だ。
こうした“エネルギーの三重苦”を根本から解決できる可能性を持つのが、「核融合発電」である。燃料のひとつであるデューテリウムという重水素は海水から得られるため事実上無尽蔵に存在し、反応が暴走しにくく、放射性廃棄物も少ない。太陽光や風力のように環境にやさしく、原発のように安定供給が可能という“夢のエネルギー”として、各国が研究開発を加速している。
政府は、AIやデータセンターの拡大で電力需要が急増する中、「安定供給と脱炭素の両立」を実現するための政策投資の重要な柱として、核融合を位置づけている。
2006年、世界で初めて実用的な核融合発電を目指す国際プロジェクトである、国際熱核融合実験炉(以下、ITER)が開始され、日本は初期段階からこのプロジェクトに参加している。
当プロジェクトにおいては、【1】投入したエネルギーの10倍以上の核融合出力を得ること、【2】プラズマを長時間安定的に維持すること、【3】核融合炉の安全性・材料・制御技術を検証すること、の3つの実証を目的としており、日本企業が主要装置の製造も担当している。
また、日本の量子科学技術研究開発機構(QST)と、EUのFusion for Energy(F4E)の共同プロジェクトとして、「JT-60SA」というITERを支える世界最大の実験炉は、日本が主導して進めている核融合エネルギー開発の中核プロジェクトであり、日本の技術水準が、“実験”から“実用化準備”段階へと着々と移行しつつある。
核融合発電の本格的な稼働目標は、原型炉が2030年代とされており、実用化に向けて巨額投資も必要だが、世界中の資金がこの分野に集まり始めている。
今回は、核融合エネルギー実用化へ向けて中核となるだろう日本企業をピックアップし、具体的にどのような役割を果たしているかを取り上げる。