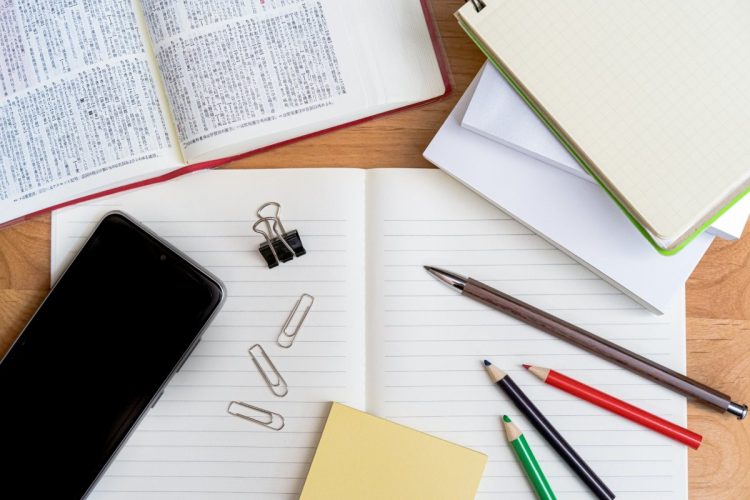推薦入試に重要な評定平均値の実態は?
大学入試が総合型選抜など推薦入試へシフトする動きが顕著となっている。推薦入試では高校の成績の評定平均値を重点的に評価することが多いという。では、実際の推薦入試では評定平均値はどのように見られているのか。『大学受験 活動実績はゼロでいい 推薦入試の合格法』が話題のノンフィクションライター・杉浦由美子氏がレポートする。【全3回の第2回。第1回から読む】
* * *
日本の大学入試制度は欧米と比べて「例外的」である。ペーパー入試の点数だけで合否を決めるやり方は欧米ではほぼ見られない。では、欧米の大学入試はどうやって合否が決まるかというと高校の成績を重視する。アメリカの最難関大学の場合、成績だけでなく、高校の難易度もしっかり見ている。日本からアメリカのトップ大学に進学しようとすると、開成や灘でもオール5に近いといった成績の生徒が有利になってくる。
これは日本でも同じである。新興のオンライン塾が「どこの高校の評定平均値も同じ評価だから、難関校では評定平均値がとりにくいので、評定平均値を高めるために通信制高校へ転校する生徒も多い」と発信しているが、これは事実とは異なる。
国立大学の公募制推薦の場合、評定平均値4.3以上が求められる。この出願要件をクリアするなら、通信制高校の方が有利だろう。なぜなら、偏差値70の難関高校で評定平均値4.3をとるのは至難の業だからだ。
だが、出願要件をクリアし出願しても、難関高校の評定平均値4.3と通信制高校の評定平均値4.3では評価は異なる。東大推薦の合格者の出身高校のほとんどが、そうそうたる難関高校で占められる理由はこれだろう。