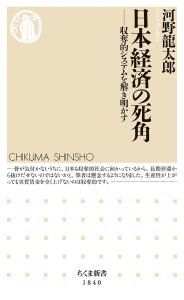長く日本経済が低迷している原因とは(イメージ。Getty Images)
高度経済成長を経て、誰もが豊かになるはずだった日本社会だが、果たして今、どれだけの人が豊かさを享受できているのだろうか──。日本経済が低迷する原因を分析した『日本経済の死角─収奪的システムを解き明かす』(河野龍太郎・著/ちくま新書)を経済評論家の加谷珪一氏が読み解く。
『日本経済の死角─収奪的システムを解き明かす』(河野龍太郎・著/ちくま新書)
* * *
本来、経済というのは、全体のパイが拡大し、皆が豊かになる方向性を目指すべきものである。実際、昭和から平成にかけての日本社会は曲がりなりにも多くの人が豊かさを実感できた。だが近年の日本経済は、富が拡大するのではなく、限られた富を皆で奪い合っているのではないか、そのような印象を持っている人も少なくないはずだ。本書はこうした疑問に真正面から答えてくれる。
著者は今の日本経済は「収奪的システム」になっていると指摘する。日本企業は過去20年にわたってそれなりに業績を拡大してきたが、従業員が受け取る賃金は横ばいのままある。企業は業績拡大を通じて得た利潤を内部留保として溜め込み、従業員に賃金として還元していない。賃金が上がらなければ消費も拡大するはずがなく、これが長期にわたる景気低迷の元凶となっている。本来、経済に備わっている分配機能が働いておらず、富が収奪されているという話だが、本書が指摘するその原因は読者の意表を突く。
一般的にイノベーションというのは、経済を成長させ賃金を増やす効果をもたらすとされる。だが著者によれば、イノベーションというのは元来、収奪的なものであり、これが賃金を抑圧しているという。
確かに自動車や電話など、かつてのイノベーションはすべての人に恩恵をもたらしたかもしれない。だが、スマホやAI(人工知能)など近年のイノベーションは必ずしも人々を幸福にしているとは限らず、しかも、そこで得られた富が一部の企業や人物に集中しているとの印象は否めない。
イノベーションが収奪的にならないよう社会全体として「飼いならす」必要があるというのが著者の主張だが、機能不全を起こしている今の政治にその役割が期待できるだろうか。その主張が的確であるがゆえに、深く考えさせられてしまう内容だ。
※週刊ポスト2025年5月2日号