■後編記事:明治以降の実業家で「芸術・芸能への投資」に最も成功したのは誰か? 小林一三の「宝塚歌劇団」は失敗の穴埋めから始まった【投資の日本史】
【プロフィール】
島崎晋(しまざき・すすむ)/1963年、東京生まれ。歴史作家。立教大学文学部史学科卒。旅行代理店勤務、歴史雑誌の編集を経て現在は作家として活動している。『ざんねんな日本史』、『いっきにわかる! 世界史のミカタ』など著書多数。近著に『呪術の世界史』などがある。
■後編記事:明治以降の実業家で「芸術・芸能への投資」に最も成功したのは誰か? 小林一三の「宝塚歌劇団」は失敗の穴埋めから始まった【投資の日本史】
【プロフィール】
島崎晋(しまざき・すすむ)/1963年、東京生まれ。歴史作家。立教大学文学部史学科卒。旅行代理店勤務、歴史雑誌の編集を経て現在は作家として活動している。『ざんねんな日本史』、『いっきにわかる! 世界史のミカタ』など著書多数。近著に『呪術の世界史』などがある。

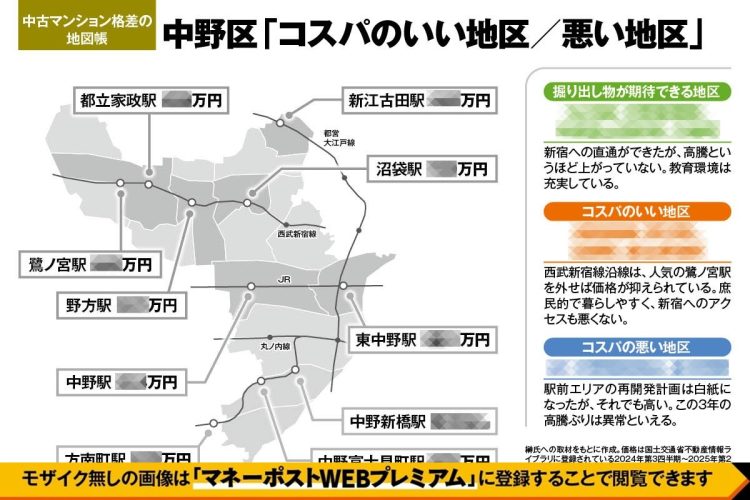
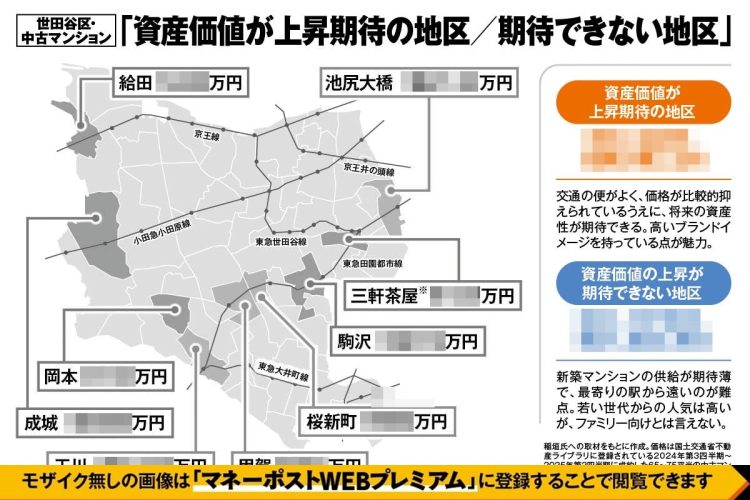

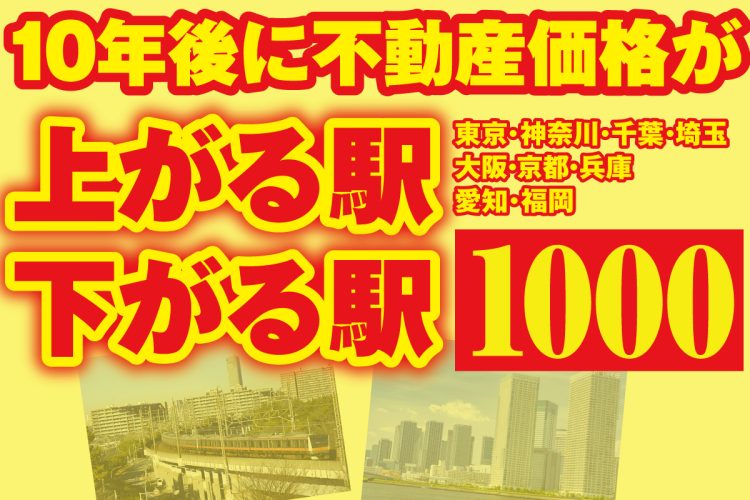




当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。