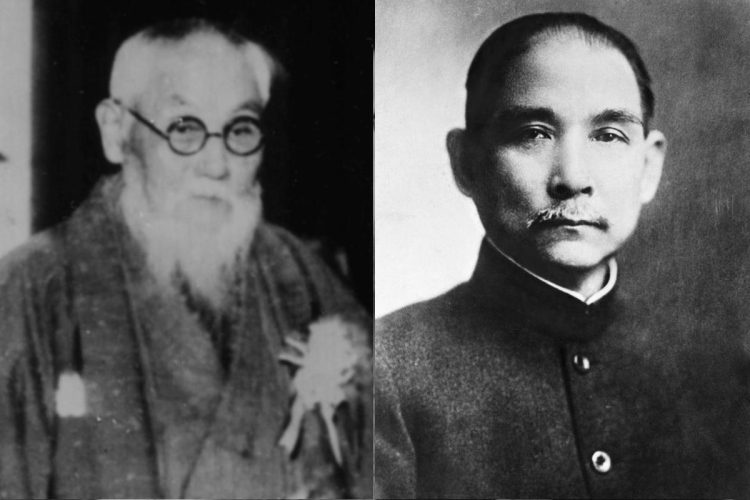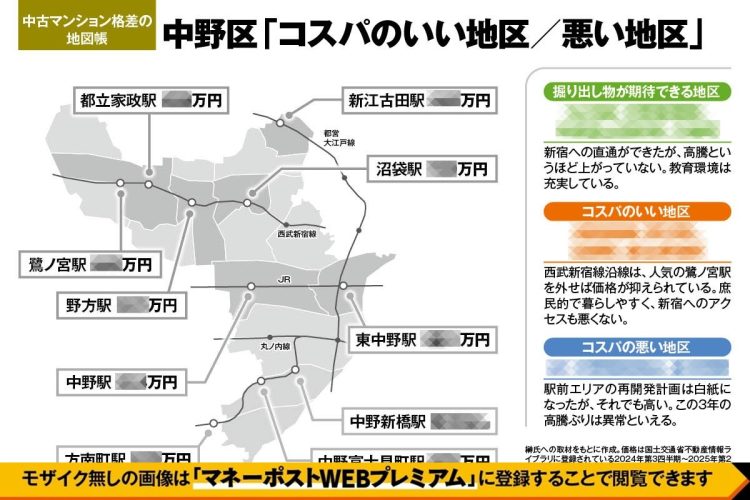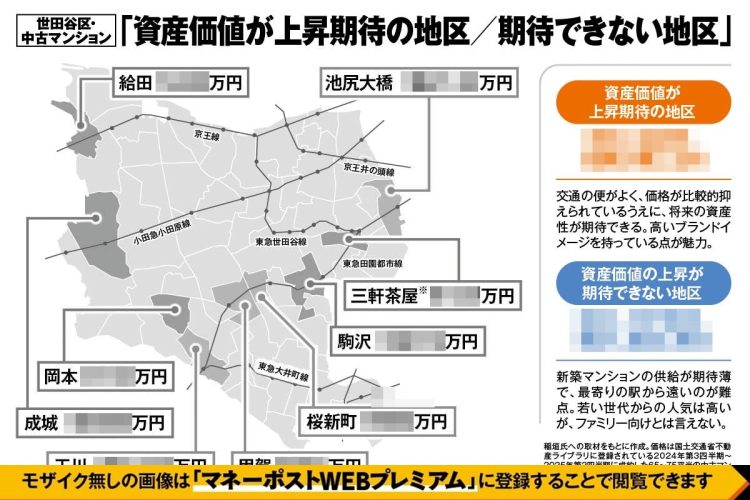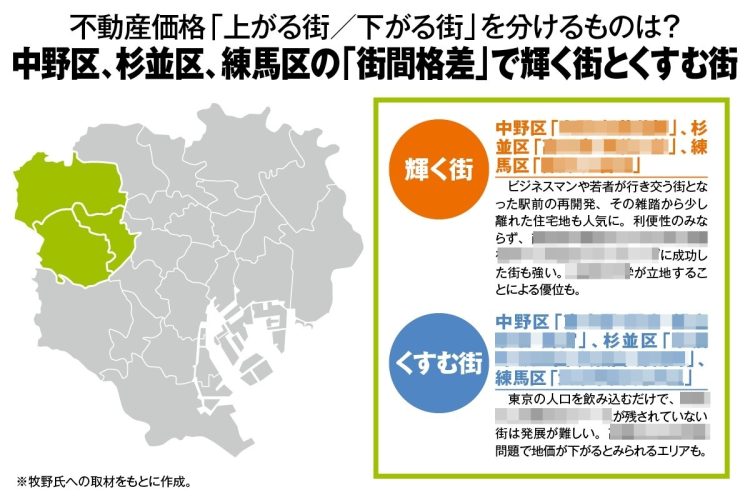孫文は日本に亡命中、頭山満邸の隣に住んでいたこともある(Getty Images)
福沢諭吉の「脱亜論」に対して「アジア主義」を唱えた頭山満らの玄洋社。クーデターに失敗し日本に逃れた朝鮮の革命家・金玉均との出会いが転機になり、中国革命の父・孫文やインドの独立運動家・ボースらへの支援につながっていく。歴史作家の島崎晋氏が「投資」と「リスクマネジメント」という観点から日本史を読み解くプレミアム連載「投資の日本史」第19回(後編)は、頭山が行なった孫文やボースへの支援により、日本が得たリターンについて考察する。【第19回・前後編の後編】
中国革命の父、インドの独立運動家をそれぞれ支援
不幸にも、金玉均はそれから間もなく上海に誘い出され、暗殺されてしまうが、頭山はそれにめげることなく、次は中華民国の北京政府から追われる身の孫文(1866〜1925年)に隠れ家を提供した。場所は東京赤坂の霊南坂。旧福岡藩主・黒田侯爵の地所で、その一帯を借り切っていた頭山は自邸の隣に孫文を住まわせた。
さらに頭山は孫文の紹介で、インドの独立運動家ラース・ビハーリー・ボース(1886〜1945年)をもかくまうこととなる。同じくインド独立運動家のスバス・チャンドラ・ボースと混同されがちだが、この2人は親戚でもないまったくの別人である。
ラース・ビハーリー・ボースはイギリスのインド総督ハーディングを爆殺しようとして失敗。偽名を使い、日本へ逃れてきた。尾行がつけられたことに気づきながら、日本には同志のネットワークがなかったため、同じくアジア人の孫文を頼り、頭山を紹介されたのである。
孫文の場合は短期間とはいえ中華民国臨時大総統を務めていたことから、日本政府にとっても北京政府を牽制する材料として有用と目されていたが、ボースの場合は事情が違った。当時の日本はイギリスと同盟関係にあっため、イギリスから外交ルートを通して抗議を寄せられれば然るべき対応をせざるをえなかった。
そこでボースに突きつけられたのが5日以内の国外退去命令。ボースはアメリカへの亡命を希望したが、当時は日本とアメリカを結ぶ定期航路がなく、いったん上海もしくは香港に赴き、船を乗り換える必要があった。当時の香港はイギリスの植民地、上海の船着き場もイギリス租界とアメリカ租界が合体した共同租界(公共租界)の内にあったから、乗り換えの際に身柄を拘束されるのが目に見えていた。
頭山満の生涯の中でも、これが最大のピンチであったかもしれない。自身の命に関わることではないが、自分が保護を約束した人物を守り切れないようでは、世間に顔向けができない。
タイムリミットが刻々と迫る中、頭山は政界に働きかけるとともに、新聞を通じて世論にも訴えかけた。新聞でボースの窮状を知り、義憤に駆られる者は少なくなかった。そこからの経緯は近代思想史を専門とする中島岳志(東京科学大学教授)の著書『中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義』(白水社)に詳しい。