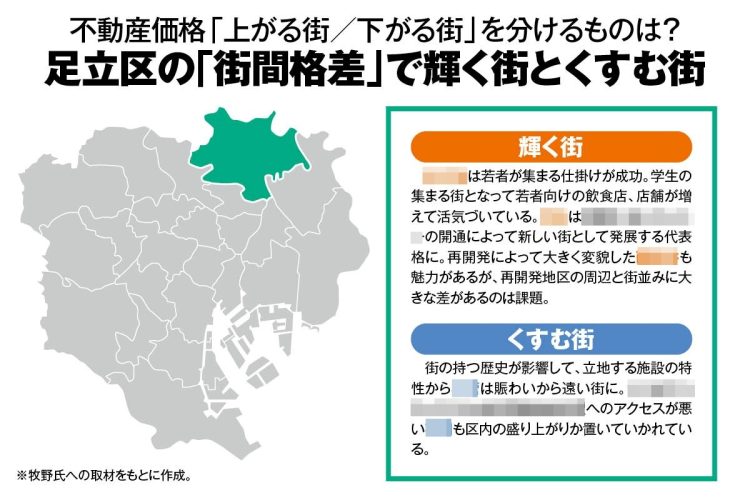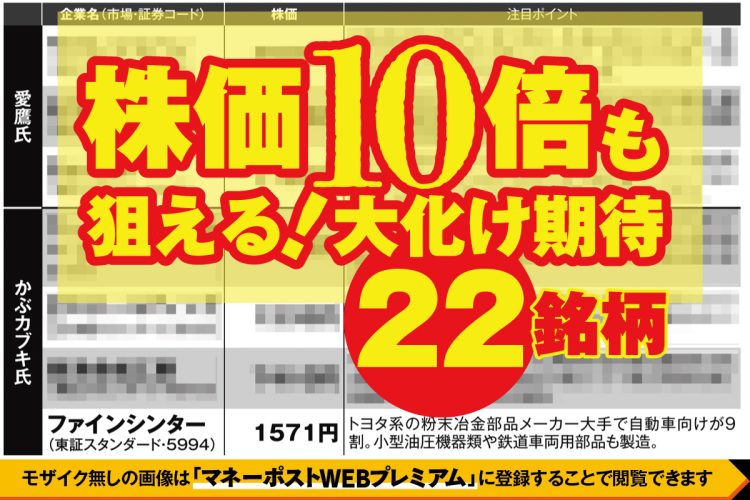コメダ珈琲店の好調の秘密はどこに?
喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」を運営するコメダホールディングスの2025年2月期決算は、売上収益が前年比8.8%増となる470億円、営業利益は88億円と過去最高を記録している。2026年2月期も増収増益を見込んでおり、その勢いは止まらない。コメダ珈琲店の好調の秘密はどこにあるのか。そのメニューと価格戦略を、イトモス研究所所長・小倉健一氏が解き明かす。
* * *
コメダ珈琲店のメニュー価格は決して安くない。「ペッパーポークとたまごの具沢山サンド」は1010~1100円(税込・店舗によって異なる。以下同)、「タンドリーチキンホットサンド」は1100~1160円、限定の「チョコノワール」は930~990円に達する。コーヒーチェーンにおける食事メニューとしては高額の部類に入る。価格だけを見れば、一般的なファミリーレストランやコンビニの弁当よりも割高に見える。にもかかわらず、コメダでの食事は多くの客にとって「コスパが良い」という評価を受けている。高いと感じる価格設定にもかかわらず、注文をためらう客は少ない。その理由は、量の多さと満足感による「得をした感覚」の設計にある。
消費者が食べ物を選ぶときには、いくつかの基準を同時に見ている。まず「味」が好みかどうか、そして「価格」が高いか安いか、「量」が自分にとって足りるかどうか、「健康に悪くないか」といったことが、無意識のうちに頭の中で計算されるているものだ。
このなかで、価格と量のバランスに関しては、「たくさん入っている方が得だ」と思い込みやすい傾向がある。実際の重さやグラム数を正確に比べることなく、見た目のボリュームだけで「安い」「お得」と感じることが多い。これは心理学では「認知バイアス」と呼ばれる。
オランダの研究者フェルメーアらの実験(『「お得感」か「健康志向」か:価格設定が食品ポーション選択に与える影響』2009年)では、飲食物のサイズと価格を変えて提示したうえで、消費者の選び方を調べた。すると、価格が内容量に正確に比例していたとしても、多くの人がそれに気づかなかった。つまり「小さいサイズが安く、大きいサイズが高い」という単純な事実を提示しても、ほとんどの人は細かい計算をしないまま、なんとなく「大きい方がお得だろう」と判断していた。数字ではなく感覚で選んでいた。目で見た印象や食べたときの満腹感が、「これだけ食べられてこの価格なら安い」と納得させる材料になる。
このような心理の働きを上手に使えば、値段が高くても「納得の価格」と感じさせることができる。店側は価格そのものを下げなくても、ボリュームや見た目の工夫を通じて「満足感」を演出できる。食べ終えたときに「高かったけどお腹いっぱいで幸せだ」と思わせることができれば、その高価格はもはや問題にならない。価格という数字よりも、体験としての「得した気分」をどうつくるかが、飲食店にとっての鍵となる。