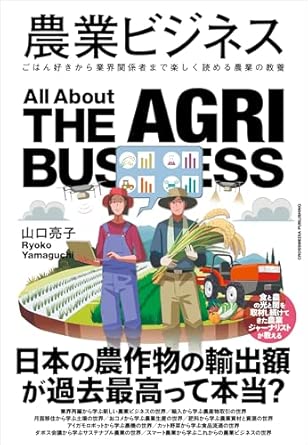「買い負け」論争に意味はあるのか
近年、食料安全保障に関連して、「買い負け」という言葉がしばしば使われます。肉や穀物、水産物を中国などの新興国に「買い負ける」といった表現がよくされてきました。「世界の食料は全体でみるとまだ余っていて、お金を払えば『買い勝てる』状況。『買い負け』という言葉は、食料安全保障とは違います」 こう話すのは、『世界食料危機』の著者で、農林中金総合研究所理事研究員の阮蔚(ルアン・ウエイ)さんです。
FAO(国連食糧農業機関)は、食料安全保障を次のように定義します。
「食料安全保障とは、すべての人々が、常に、物理的、社会的、経済的に、活動的で健康的な生活のために、食の嗜好(しこう)と食事のニーズを満たす十分かつ安全で栄養のある食料を入手できることを意味する」
つまり、日本の商社が意のままに食品を調達できなくなったからといって、すなわち食料安全保障が損なわれている……とはならないのです。
経済成長を遂げた中国は今、世界中でさまざまな食料を買い付けています。日本は以前から旺盛に買い付けていただけに、より高い価格で買っていく中国に「買い負けている」と感じるに過ぎません。「これはごく自然なこと」だと阮さんは言います。
この買い負けという言葉は、特に肉や飼料穀物で使われます。中国が輸入を増やしているため、将来的に日本がこうした農畜産物を調達しにくくなるというのです。阮さんは次のように指摘します。
「中国だけでなく、東南アジアやインドも、経済成長につれて食肉の消費が増え、輸入を伸ばしていくはずです。特に宗教上の理由から食肉の消費が極めて少ないインドは、1人当たりの消費量がわずかに増えただけでも、14億という人口を擁するだけにかなりのインパクトを与えます」
インドは1人当たりの食肉消費量が極めて少なく、それと連動して飼料穀物の消費も少なくなっています。それだけに肉食が拡大すると、世界に大きな影響が出るのです。
要は、中国の動向いかんにかかわらず、食肉と穀物の争奪戦が激しくなるのは避けられないというのです。日本がこれまで通りに食料を買い付けたいなら、以前より高値を払う必要が出てきます。
「もし輸入品の価格が一定のレベルより高くなると、逆に国産に競争力が出てきます。まだそこまで至っていないので、国内で増産しても輸入品に価格で勝てないし、輸入するにしても昔より高くつくという中途半端な状況なんですね」
この状況を脱するには、経営の大規模化や技術革新などで生産コストを引き下げ、国産を輸入品と競争できる価格に持っていくことが考えられます。
「ただ穀物の場合、輸入品と競合できる価格に自然に持っていけるとは考えにくい。生産者に所得補償をするなり、補助金を出すなりして支えることを検討すべき時期に来ていると感じます。国民的な議論をして、どうするのがよいか考えるタイミングではないでしょうか」(阮さん)
※山口亮子著『農業ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)より一部を抜粋して再構成。
(了。第1回から読む)
【著者プロフィール】
山口亮子(やまぐち・りょうこ)ジャーナリスト。愛媛県出身。京都大学文学部卒、中国・北京大学修士課程(歴史学)修了。時事通信社を経てフリーに。雑誌や広告などの企画編集やコンサルティングを手掛ける株式会社ウロ代表取締役。著書に『ウンコノミクス』(インターナショナル新書)、『日本一の農業県はどこか 農業の通信簿』(新潮新書)、共著に『人口減少時代の農業と食』(ちくま新書)、『誰が農業を殺すのか』(新潮新書)などがある。日本の食と農に潜む課題をえぐり出したとして、食生活ジャーナリスト大賞ジャーナリズム部門(2023年度)受賞。