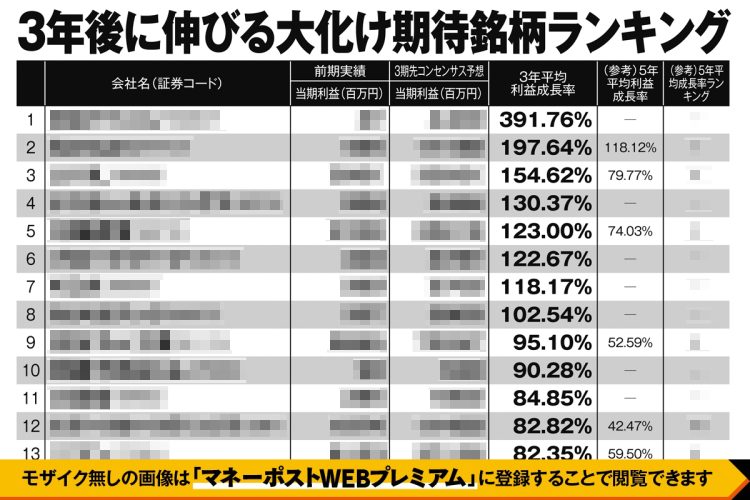相手に確実に伝わる言葉をどう作るか?(イメージ)
商品説明、サービス紹介、企画書、プレゼン資料――相手に伝えるために専門用語や業界用語などの言葉を選んでいないだろうか。難しい表現を使えば専門的に見え、価値が伝わると考えがちだが、実際には逆効果になることがある。相手の経験とつながらない言葉は、むしろ心の距離を遠ざけてしまうのだ。Webメディア編集者として7000本超の記事タイトルを考案し、数万本のデータを分析してきた武政秀明氏の著書『22文字で、ふつうの「ちくわ」をトレンドにしてください』より、相手に確実に伝わる言葉の選び方について解説する。
「わかりにくさ」の誤解
私たちは時として、難しい言葉を使えば専門性が高まり、きれいな表現を選べば価値が伝わると考えてしまいます。でも、本当にそうでしょうか。
「フィードバック」という言葉と「上司が部下の仕事について評価・指導すること」という表現。「ICT教育」と「タブレットやパソコンを使った授業」という表現。同じ内容を指していても、その言葉から受け取れる具体性は大きく違います。
表現の格調の高さは、必ずしも伝わりやすさを意味しない。むしろ、相手の経験とつながらない言葉は、心の距離を遠ざけてしまうことさえあるのです。
たとえば「地域コミュニティ」も抽象的な響きを持つ言葉です。「地域」「コミュニティ」と言われても、どこかの地域で誰かがなんらかの役割で集まっているくらいの漠然としたイメージしか浮かびません。でも「地域の顔見知りが集まる場所」と言えば、「お祭りの時に集まって準備してくれていた人がいたな」とか、「ご近所でよく立ち話していたな」とか、誰もが思い浮かべられる風景があるはずです。
くれぐれも自分の知っている言葉が相手に伝わると思い込んでしまってはいけません。「この専門用語は格好いいから使おう」「この業界用語を使えば、くわしそうに見えるはず」。そんな思い込みが、かえって相手との距離を作ってしまうのです。