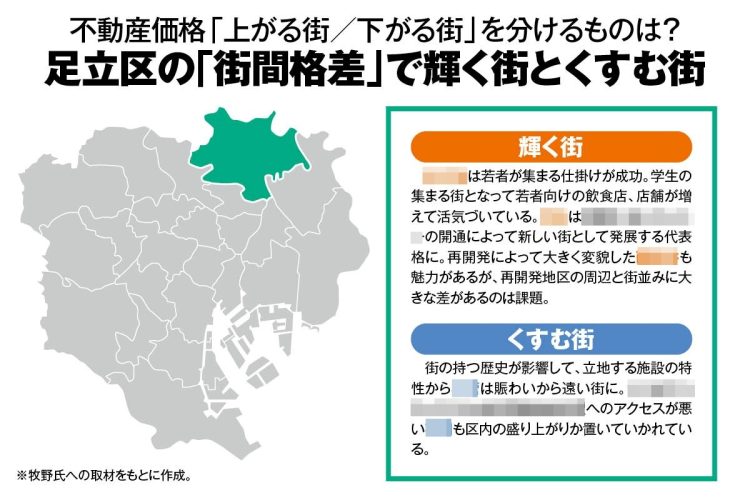生成AIの普及で新たな問題も(写真:イメージマート)
学歴至上主義の中で厳しい就職難が常態化し、格差が広がる中国社会。そんななかで、日本の大学院に進学し、修士号取得を目指す中国人留学生が増加している。シリーズ「中国人留学生だらけの日本の大学院」、第4回では中国人留学生の著作権意識の低さや、昨今のAIの普及などを受けて新たに浮上している問題について現場の声を紹介する。【全4回の第4回。第1回から読む】
著作権や引用など最低限のルールを知らないケースも
都内の私立大学で中国人院生の指導をしている教授・Aさん(50代女性)は、留学生たちの研究倫理意識の低さに警鐘を鳴らす。
「研究者には、捏造、改竄、盗用(コピペ)をしないという研究倫理があります。これは文系も理系もかならず守らなくてはならない最低限のルールです。しかし、研究者志望ではない一部の中国人院生は、これらのルールをまったく知らないケースがある。『自分で勉強した内容は私の頭で考えたことと一緒』『どこかで勉強したから自分の主張として書く』といった著作権意識がないパターンが多く、心構えの初歩から教える必要があります。
他大学の教員からも『中国語の参考文献が増えるため、教員も剽窃のチェックが難しいよね』というため息が聞こえてきます。もちろん、こうした問題は中国人に限った話ではないですし、優れた院生がいることも事実。ただし、日本の大学院を“研究には興味がないが、中国での就職のためにお手軽に修士号が取れる場所”と考えて留学する人は、研究倫理を軽んじやすい傾向にあると思います」(Aさん)