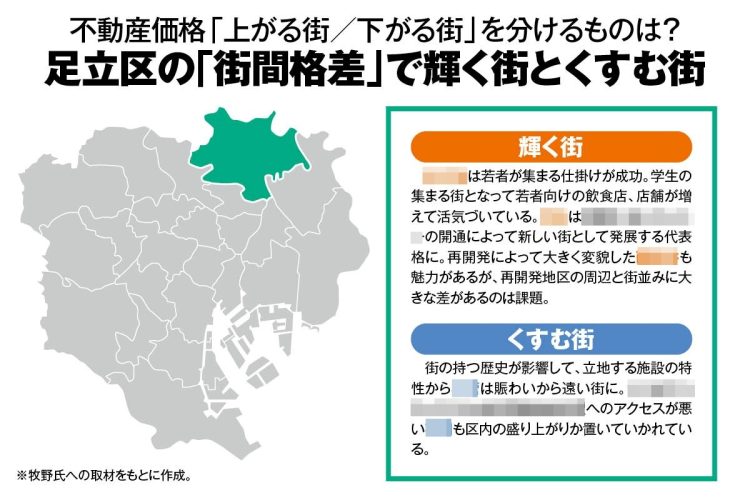原発新増設に対する国民の疑念が払拭される日は来るのか(イラスト/井川泰年)
関西電力が次世代型原発の建設に向け、地質調査を開始すると発表した。原発の建設が実現すれば、2011年の東日本大震災後では初の新設となる。こうした動きに、日立製作所の元原子炉設計者で経営コンサルタントの大前研一氏は「今の日本にとって“唯一の選択肢”だが、問題も孕んでいる」と指摘する。どういうことか、大前氏が解説する。
* * *
関西電力が美浜原子力発電所(福井県美浜町)の敷地内で新たな次世代型原発の建設に向けて地質調査を開始すると発表した。美浜原発は、すでに1号機と2号機が運転を終了し、現在稼働中の3号機も2026年に運転開始から50年を迎えるため、リプレース(建て替え)を目指すものだ。
新設する原発は、三菱重工業が開発を進めている「革新軽水炉」の「SRZ-1200」。出力は120万kW級で、3号機(82.6万kW)の約1.5倍だ。
実現すれば、2011年の3.11(東日本大震災)の福島第一原発事故後初めての新設となり、私はこれを日本の原子力政策が“再稼働”から“再建設”に移行する兆しだとみている。
日本では、3.11以前は原子力発電が総発電力量の30%前後を占めていたが、2023年度は8.5%にとどまっている。
一方、世界各国の原子力発電比率は、フランスの64.8%を筆頭に、ウクライナ、スロバキア、ベルギーが50%以上、ハンガリー、スウェーデン、韓国などが30%以上だ。豊富な石油・天然ガス資源を持つアメリカやロシアの原発比率は18%台。石炭火力に頼る中国は4.9%、インドは3.1%だが、それぞれ新たに26基、7基の原発を建設中である。日本は世界から取り残された状態にあるのだ。
結論から先に言えば、関西電力の原発リプレースは、今の日本にとって“唯一の選択肢”だと思う。だが、問題も孕んでいる。以下、その理由を説明したい。
今や日本の原発は、ほぼすべてが老朽化している。
もともと原発の運転期間(耐用年数)は40年と定められていたが、福島第一原発事故を機に、原発の新増設にブレーキがかかったため、「原則40年、原子力規制委員会が認めれば最長20年間延長できる」と変更された。
さらに今年6月からは、60年の上限は維持しつつ、規制委の審査や裁判所の命令、行政指導などで停止した期間は運転期間のカウントから除けることになった。除外期間が15年なら最長75年間運転できることになるが、これはあまりにもリスクが高い。
しかも、“延命”したところで、先は見えている。最も新しい原発は2009年に運転を開始した北海道電力の泊3号機で、2027年の再稼働を目指しているが、そうなったとしても60年後には今ある原発はすべて運転停止となる。
では、どうするか?