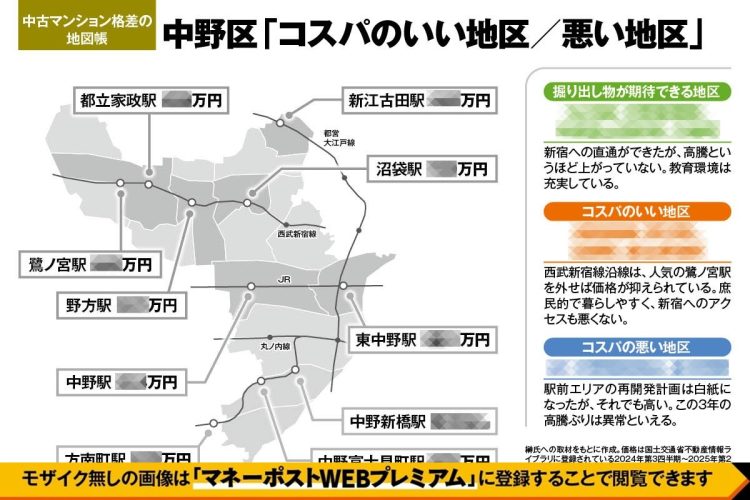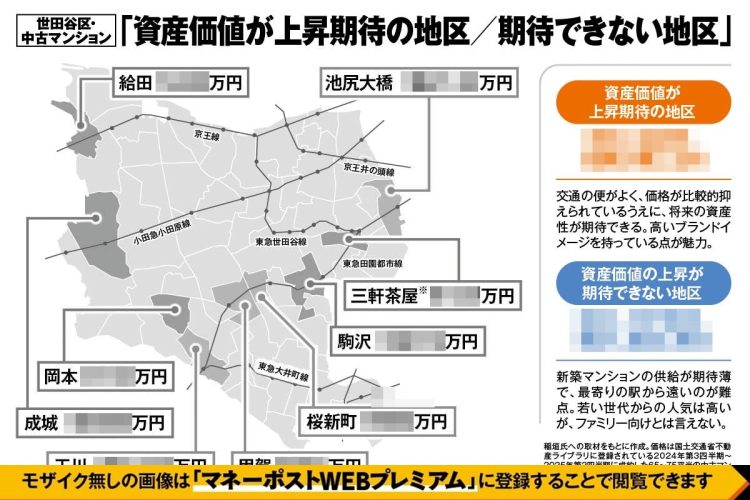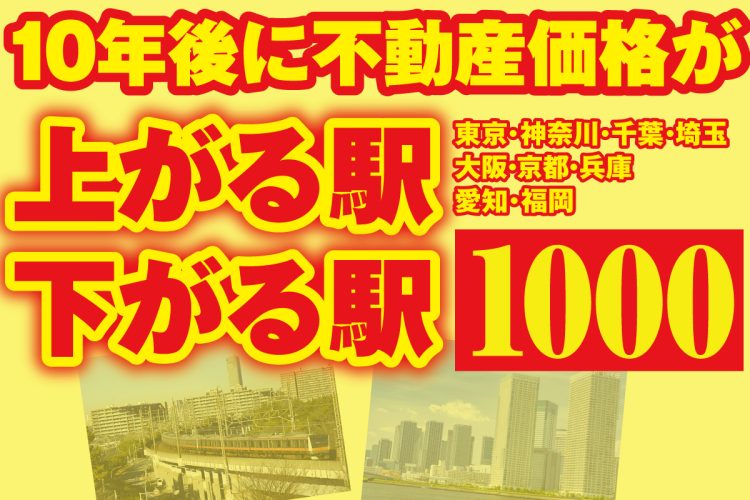苦境の焼肉チェーンのなかで「焼肉きんぐ」が絶好調の理由とは
焼肉店の倒産件数が増加していると報じられるなか、大手チェーンの中で唯一気を吐いているのが「焼肉きんぐ」(物語コーポレーション運営)だ。日本ソフト販売株式会社による〈【2024年版】焼肉チェーンの店舗数ランキング〉によると、2024年7月時点の焼肉チェーンの店舗数ランキングは1位が牛角で、2位が焼肉きんぐ、3位が七輪焼肉安安。そのなかで前年同月比プラスなのは、306店から325店へと増加した焼肉きんぐのみ。焼肉きんぐ“一人勝ち”ともいえる絶好調の秘密はどこにあるのか。他チェーンとは異なるその戦略を、イトモス研究所所長・小倉健一氏が解き明かす。