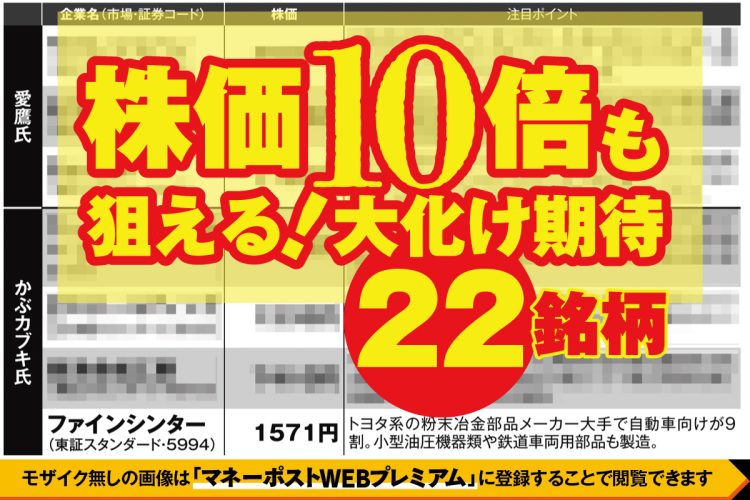今回の処分が宅配業界再編の呼び水になるかもしれない(日本郵政の根岸一行・新社長/時事通信フォト)
配達員の酒気帯び状態での勤務を見逃してきた日本郵便の「不適切点呼」問題。全国の郵便局で違反が常態化していたことを受け、国は日本郵便の運送事業許可を取り消す処分を下した。実はこの重い処分の裏に、宅配の一角を担う「ゆうパック」を廃止するという政府の思惑があると指摘されている。
国交省「令和5年度宅配便(トラック)取扱個数」によると、宅配便のシェアは最大手がヤマト運輸の宅急便(46.7%)で、以下に佐川急便の飛脚宅配便(27.9%)、日本郵便のゆうパック(20.5%)が続き、大手3社で全体の95%に至る寡占状態となっている。その一角を占める日本郵便に対する今回の処分の影響は、日本の物流網全体に及ぶ。
もともと利益が少ない郵便事業のコストが跳ね上がる
日本郵便は、使用停止となったトラックの代替として、約6割分の輸送をヤマト運輸や佐川急便、子会社などに委託し、約4割を自社の軽貨物で代用する方針だ。
流通経済大学教授で、国交省の有識者会議にも参加する矢野裕児氏は日本郵便の経営への影響は大きいと指摘する。
「これまで自社で賄っていた分を外部に委託すると、人件費をはじめとして様々な外注費がかかります。どれほどの額になるか未定ですが、もともと利益が少ない郵便事業のコストが増せば、ゆうパックの赤字化がさらに進む可能性が高い」
戦略物流専門家でイー・ロジット会長の角井亮一氏はその影響が業界全体へ波及すると見る。
「本来なら処分を受けた車両を譲渡したうえで職員を出向させるべきですが、労働組合が強い日本郵便は外部に職員を出向させられないようです。このため処分で使えなくなった2500台に乗っていた人員の雇用を維持するコストもかかります。
しかも人手不足のなか、外注する作業員の人件費は通常より割高になるはずで、業界全体でドライバーの人件費の相場が上がるかもしれません」
さらに国交省の処分が3万2000台もの軽貨物に及ぶと、そのインパクトは計り知れないと角井氏は指摘する。
「日本郵便の軽貨物の事業許可が取り消されれば、ゆうパックの事業を継続することが困難になります。国内シェア2割という規模の大きさから今回のように外部に委託することも難しく、ゆうパックを丸ごと売却する可能性が浮上します」
今回の処分は宅配業界再編の呼び水となるかもしれないのだ。