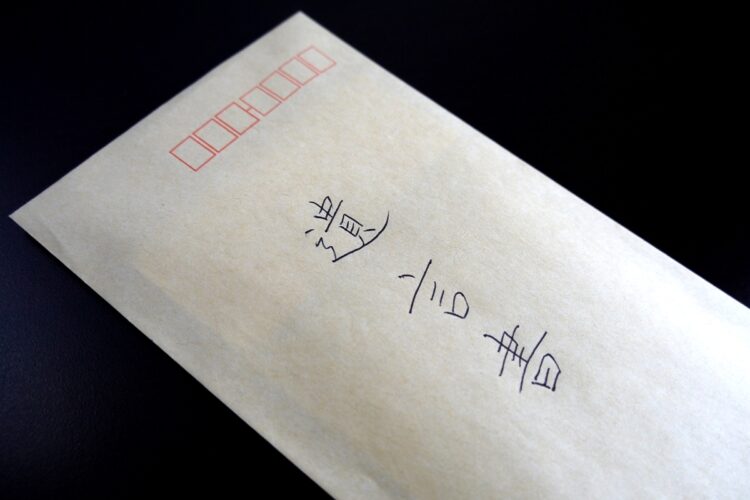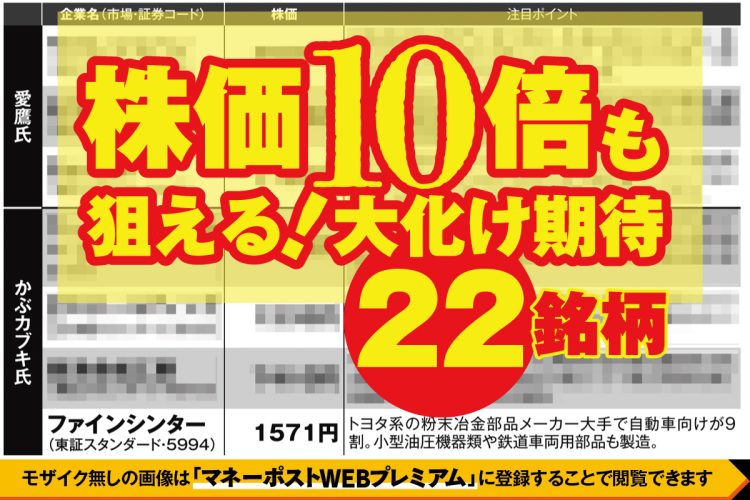「義父母の相続」でトラブルを避けるためには(イメージ)
自分がどこまで口を出していいのか、頭を悩ませるのが「義父母の相続」だ。部外者だからとつい遠慮してしまいがちだが、何もしないと実親以上の面倒ごとが降りかかり、金銭的にも損するケースが珍しくない。揉めずに相続を進めるための交渉の鉄則を学ぶ。
長男偏重になるケースが目立つ
大阪府在住の60代男性の妻は、自分の父母の病院の送り迎えなど身の回りの世話を一人で担っていた。ところが義父に続いて義母が亡くなった際、夫婦は驚いたという。母の遺言書は「長男(妻の兄)に7割、長女(妻)に3割の財産を渡す」という内容だったのだ。
「実家から離れて住む長男は両親の面倒を全然見ず、妻はパートを辞めて介護に付きっきりでした。遺言内容には大いに疑問がありますが、義兄は当然のように相続について主張をするし、何より関係を拗らせたくない」(60代男性)
相続問題解決の専門家である夢相続代表の曽根恵子氏が言う。
「嘆かわしいことに、日本では女性がいくら高齢の親を世話しても、“よその家に嫁に行ったのだから”と相続で不利になるケースが多い。特に男の兄弟がいると長男偏重になるケースが目立ちます。なかには親の世話をしてきた長女と何もしない長男で相続の割合が1対9だったという事例もあります」
こうした状況で難しい立場に置かれるのが夫だ。妻が親の世話で苦労しているのを傍目に見ていたとしても、相続では口を出しづらい。
「妻のきょうだいからすれば“おまえは口を出すな”といった心境でしょう。しかし、我慢するだけではなく、夫にこそやれることがあります。妻は親を亡くした悲しみに沈んでいても、夫は自分ごとではないため割と冷静でいられます。夫が正しい知識をもって妻をサポートすると上手くいきやすい」(曽根氏)
気をつけたいのが介入の仕方だ。
「しゃしゃり出ると必ず揉めます。夫はあくまで第三者として中立を保ちつつ、見えないように妻をアシストするのが大切です」(同前)
生前から死後まで、義父母の相続をスムーズに進めるための鉄則を解説する。