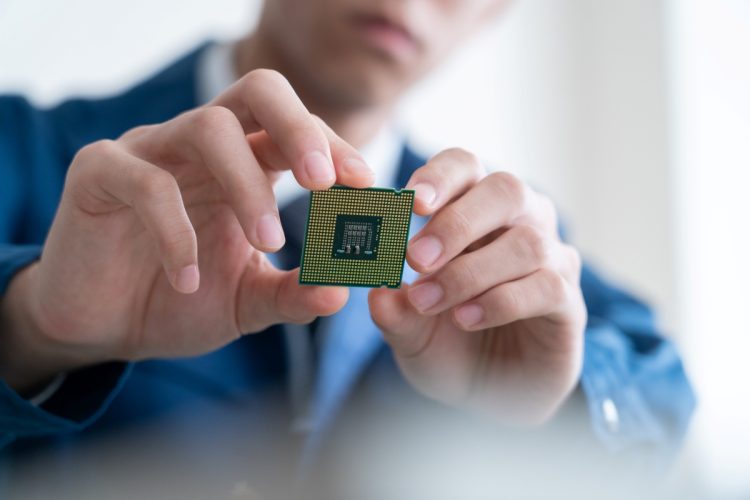AIチップへの需要は依然高い(写真:イメージマート)
高市政権の誕生により日経平均株価は5万円を突破。その後、米国のAI関連株が割高だとの警戒感から下落局面もあったが、今後はどういった見通しになるのか。元証券マンの個人投資家で、『決算書3分速読から見つける10倍株ときどき50倍株』(KADOKAWA刊)の著書があるかぶカブキさんに聞いた。
かぶカブキさんは、元手94万円を1年11か月で1646万円に増やし、自己資産を17.5倍にした実績がある。大学卒業後はIT関連企業を経て、証券会社に就職。ディーラーや営業の経験を通じて大化け銘柄の発掘を確立したという。2021年に38歳で独立した、“テンバガー(10倍株)”発掘の達人として知られる。
「高市トレード」の実態は
日経平均株価の史上最高値更新をもたらしたとされる「高市トレード」について、かぶカブキさんはどう見ているのか。
「もちろん高市(早苗)氏が首相に就任したことの影響もあると思いますが、AIのデータセンター関連のハード製造装置や半導体の材料・部材への投資が伸びていることが大きいのではないかと見ています。もちろん、高市首相もAI・半導体関連への成長投資を掲げており、それが相まっての伸びではなかったか。
AIバブルが弾けるのではないかという懸念も浮上していますが、マイクロソフトやメタがAIのデータセンターへの設備投資をさらに増加させるとしています。AIチップへの需要は高まっており、半導体メモリのひとつであるDRAM価格の急上昇の状態が続いている。高い需要に対して供給が少ない状態が続いているわけです。日経平均には半導体関連の銘柄が多くあるので、下がる心配より、まだまだ上がるという期待のほうが大きいのではないかと見ています」(以下、「」内コメントはかぶカブキさん)
今後、日経平均はどこまで伸びるのかについてはこう話す。
「具体的に日経平均がどの水準まで達するのかは不透明ですが、業績のピークが続かないという見方が広がった時に株価急落が始まると考えるのが一般的です。警戒すべきは設備投資を減らす動きがあった時で、その時は売る判断をするということじゃないでしょうか」