どこにでも置ける本籍に何の意味があるのか(イラスト/井川泰年)
今年5月の改正戸籍法施行で、戸籍の氏名に振り仮名が記載されるようになった。振り仮名があることで不正防止に役立つというが、経営コンサルタントの大前研一氏は、「戸籍制度は、21世紀のデジタル時代に対応したものに定義し直さなければならない」と主張。大前氏が提言する。
どこにでも置ける本籍に何の意味があるのか(イラスト/井川泰年)
今年5月の改正戸籍法施行で、戸籍の氏名に振り仮名が記載されるようになった。振り仮名があることで不正防止に役立つというが、経営コンサルタントの大前研一氏は、「戸籍制度は、21世紀のデジタル時代に対応したものに定義し直さなければならない」と主張。大前氏が提言する。



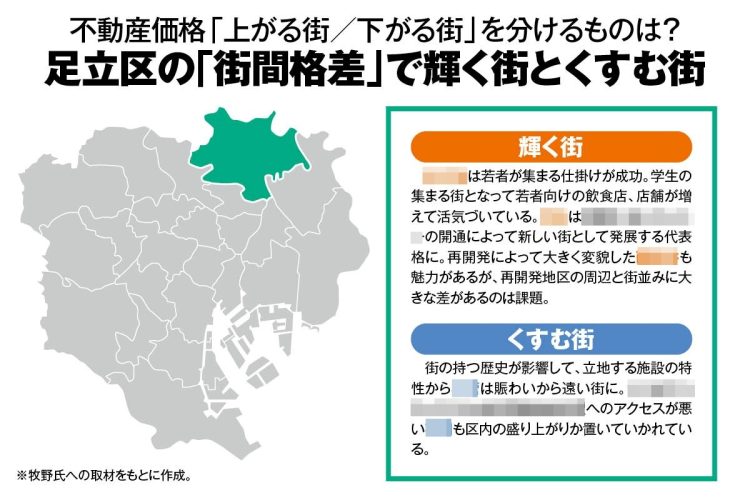





当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。