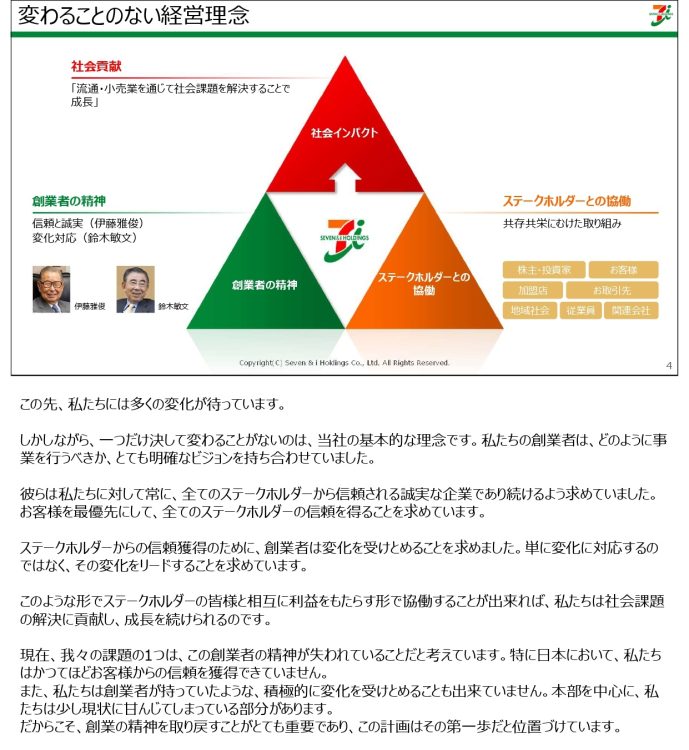痛烈な自己批判にあふれる「7-Elevenの変革」資料
復活のための3つの具体的な処方箋
では、失われた信頼と革新性を取り戻すために、企業は何をすべきなのか。そのヒントは、顧客の声と現場への信頼にある。
2011年に学術誌「Organization Science」で発表された論文「顧客との対話とイノベーションの連関:新たな組織的実践の媒介的役割」(ニコライ・J・フォス、ケルド・ローレン、トーベン・ペダーセン)は、顧客の声とイノベーションの間に存在する組織的な課題を、実証データを用いて解明した点で世界的に高く評価されている。
顧客との対話は、それだけでは直接イノベーションには結びつかない。顧客の声をイノベーションに昇華させるためには、それを可能にする社内の組織的な仕組みが不可欠であると論じている。論文は、復活のための3つの具体的な処方箋を示唆する。
第一の処方箋は、現場への大胆な権限移譲である。論文は、顧客と多く対話する企業ほど、従業員へ責任と権限を移譲する傾向があると指摘する。顧客と直接接する現場の従業員こそが、顧客のニーズに関する優れた知識を持っている。彼ら/彼女らが迅速に意思決定できる環境こそがイノベーションの土壌となる。セブンに当てはめれば、本部主導の画一的な方針ではなく、各地域の店長や店舗指導員が、顧客の声をダイレクトに品揃えやサービス改善に反映できる裁量を持つことが求められる。
第二の処方箋は、部門の壁を越えた徹底的な情報共有である。論文によれば、権限移譲は社内の情報伝達を活発にする効果を持つ。そして活発な情報伝達こそが、イノベーションのパフォーマンスを向上させる。商品開発、マーケティング、店舗運営といった各部門が縦割りで動くのではなく、顧客から得られた情報を組織全体で共有する。SNSで批判された上げ底の問題や味の低下といったネガティブな情報こそ、全部門で共有し、迅速な改善につなげる文化が必要である。
第三の処方箋は、顧客志向の従業員が報われるインセンティブ改革である。権限移譲が進んだ企業は、知識の獲得や共有に対する報酬制度を導入すると論文は分析する。短期的な売上目標だけでなく、顧客の信頼獲得に貢献するような行動を正当に評価し、報いる仕組みを構築することが重要となる。顧客からの感謝の声や、長期的なファン作りに貢献した従業員が評価される人事制度が、組織全体のベクトルを顧客に向ける力となる。
セブンが直面する危機の本質は、個々の商品の問題にとどまらない。顧客との対話という掛け声だけでは、消費者の心は戻らない。顧客の声を受け止め、組織の隅々まで浸透させ、迅速に形にする。その一連の流れを機能させるための組織的な大手術こそが、絶対王者が信頼と輝きを取り戻すための道ではないだろうか。
【プロフィール】
小倉健一(おぐら・けんいち)/イトモス研究所所長。1979年生まれ。京都大学経済学部卒業。国会議員秘書を経てプレジデント社へ入社、プレジデント編集部配属。経済誌としては当時最年少でプレジデント編集長就任(2020年1月)。2021年7月に独立して現職。