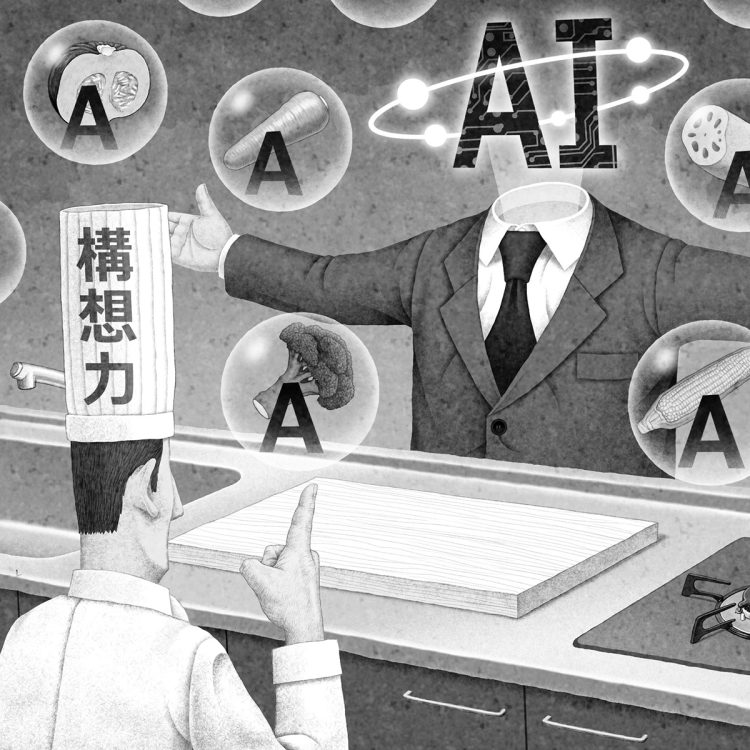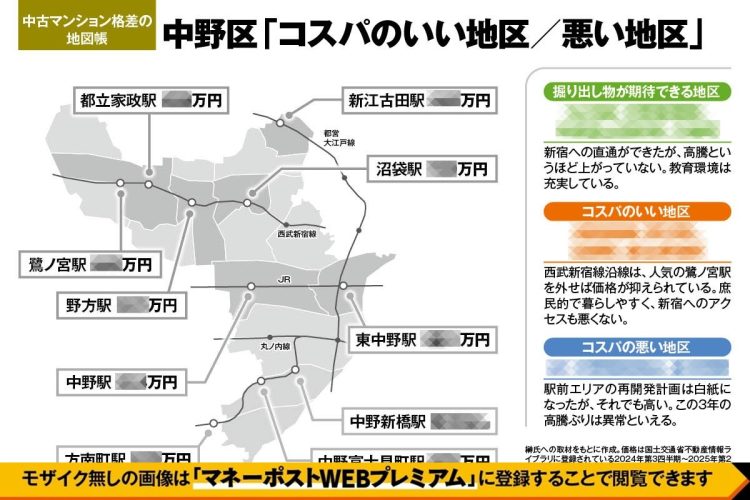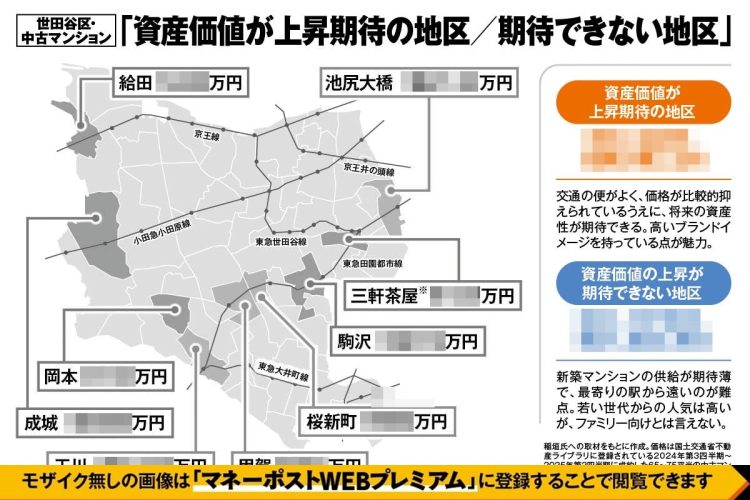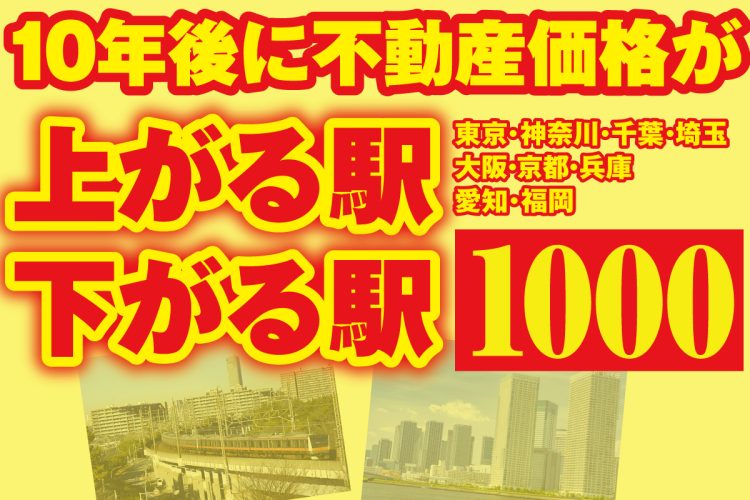AI時代に求められるのは「構想力」(イラスト/井川泰年)
急激な進化を遂げている生成AI(人工知能)。経営コンサルタントの大前研一氏は「個人の仕事レベルでもAIの影響は大きくなっている」と指摘する。AI時代に仕事はどう変化していくのか。また、AIをどう活用すればよいだろうか。大前氏が解説する。
* * *
政府は9月1日、AIの利用拡大を目指す「AI戦略本部」を内閣府に設置した。遅れている日本のAIの利活用や研究開発を促すため、冬までに基本計画を策定するそうだが、あまりに遅きに失しているし、政府が号令をかけたところで、そう簡単に遅れは挽回できないだろう。
2022年に「チャットGPT」が公開されて以来、すでにAIは社会に劇的な変化をもたらしている。
たとえば、アメリカ経済を牽引している「マグニフィセント・セブン」――GAFAM(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、マイクロソフト)にエヌビディアとテスラを加えた7社――をはじめとする大手テック業界では、AI開発への投資を拡大するための効率化に伴う大規模リストラが加速している。
先頭を切っているのはマイクロソフトで、5月に約6000人、7月に約9000人をレイオフ(一時解雇)した。その主な対象は、AIが業務を代替できるプログラマーや従来型の営業職だった。グーグル、アマゾン、IBM、HP(ヒューレット・パッカード)なども大がかりなレイオフを進めているとされる。AIを進化させるために、人間がAIに職を奪われるという皮肉な状況になっているのだ。
個人の仕事レベルでもAIの影響は大きくなっている。たとえば、ネット検索。もともと1998年にグーグル検索がリリースされて情報は“ググる”ことが当たり前になったが、最近のグーグル検索はAIの導入によって検索結果を要約してくれるまでに進化した。
単に関連サイトを提示するのではなく、いきなりAIが回答する「AIモード」や「AIによる概要(AI Overview)」が表示されることも増えている。すぐに要点がつかめる上、疑問があったらAIに質問を繰り返していけば、自分が知りたいことはだいたいわかる。AIの判断によって「答えは数秒で入手できる」時代になったのである。
検索だけでなく、ビジネス分野では「AIエージェント」が登場し、さらに「エージェント型AI」の開発も進んでいる。
前者は人間の意思決定を模倣して問題をリアルタイムで解決するために自律的にタスクを実行し、資料作成やプログラミング、商品開発など様々な仕事をAIがこなす。後者は複数の専門的なAIエージェントで構成され、高度で複雑な目標を達成するために必要なAIエージェントを連携させてタスクを遂行する。つまり、エージェント型AIは1つの「プロジェクトチーム」や「事業部」のようなものなのだ。
したがって当然、これから仕事のやり方は激変し、AIエージェントで代替できる業務を行なってきた人間は、どんどん不要になっていくのである。