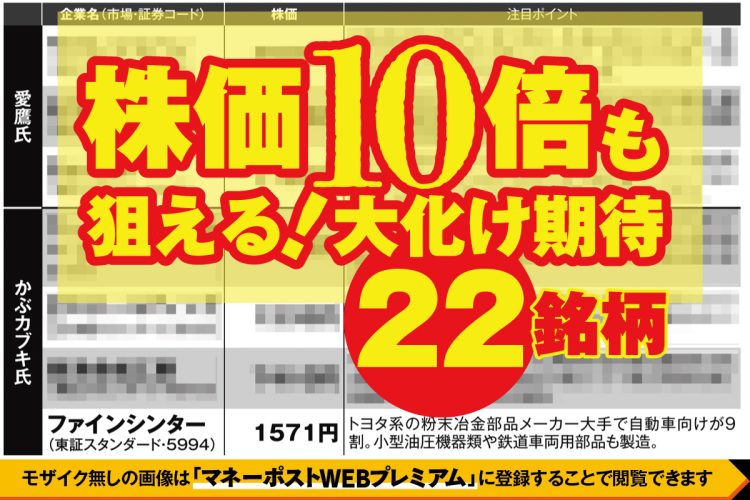米中関係はこれからどうなる?(イラスト/井川泰年)
アメリカと中国の対立が続いている。経営コンサルタントの大前研一氏は「米中のつばぜり合いは、今後ますます激しくなる」と指摘する。今後の米中関係の行方はどうなるのか、大前氏が読み解く。
* * *
このところ、中国が“主役”となって世界をリードする場面が目につく。
たとえば、9月3日に北京の天安門広場で開催した「抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念式典」では、ロシアのプーチン大統領や北朝鮮の金正恩総書記ら26か国の首脳を招待し、習近平国家主席が閲兵して大規模な軍事パレードを行なった。式典では迎撃が難しい極超音速対艦ミサイル、新型ステルス戦闘機、核ミサイルに加え、各種のドローンや犬型ロボットなど多様な無人システムの新兵器が公開された。
しかし、そもそも抗日戦争で旧日本軍と主に戦ったのは蒋介石の中国国民党軍であり、毛沢東の中国共産党軍ではなかった。また、「世界反ファシズム戦争勝利」というのも、現在の中国、ロシア、北朝鮮こそ独裁・全体主義のファシズム的な政治体制だから、笑止千万なのだが、中国は台湾侵攻、対米衝突も見据えて、ロシアや北朝鮮などとの“枢軸同盟”の形成を世界に誇示する格好になった。
さらに、中国はそれに先立ち、経済分野では9月1日に上海協力機構(SCO)総会を天津で開催した。SCOは中国とロシアが中核となり、インドや中央アジア諸国など10か国による枠組みで、習近平国家主席はSCO加盟国に対して、年内に20億元(約420億円)の無償支援を行なうなどの支援を約束した。それによってグローバルサウス(南半球の新興国・途上国)を取り込み、人民元を基軸通貨とする“中国版ブレトンウッズ体制”を構築してアメリカが主導する政治・経済の世界秩序に対抗しようとしているのだ。
その中国に対し、アメリカのトランプ大統領は、当初こそ厳しい姿勢で臨んでいたが、今は腰砕け状態になっている。
たとえば、いったん最大145%の追加関税を課したものの、その後の通商協議で対中相互関税を125%から34%に引き下げ、さらに国・地域別関税率24%の適用を11月10日まで延期した。日本をはじめとする他の国々には重い関税を課しながら、中国には大甘な対応をしているのだ。
あるいは、中国発の動画共有アプリ「TikTok」。それに対して使用規制をかけ、親会社の中国企業バイトダンスにアメリカ事業をアメリカ側へ売却するよう迫っていたはずが、今年1月に施行された同アプリ禁止法の執行を4回も延期し、8月にはホワイトハウスの公式アカウントまで開設するという実に摩訶不思議な迷走状態だった。
結局、アメリカの企業連合が買収することになったが、中国側が何らかのキルスイッチ(緊急停止装置)を持つかもしれない。
さらに8月下旬には、それまで学生ビザ(査証)の審査を厳格化するなど厳しい姿勢をとってきた留学生政策を突然、180度方針転換し、60万人もの中国人留学生を受け入れる意向を示した。その理由は、中国人留学生がいなくなったらアメリカの大学が廃業に追い込まれるというものだ。これにはトランプ大統領の支持基盤である「MAGA」(Make America Great Again=アメリカを再び偉大に)派からも批判が相次いでいる。
ことほどさように、トランプ大統領の対中政策は支離滅裂で首尾一貫していない。習近平・中国にとって、“単細胞”で「TACO」(Trump Always Chickens Out=トランプはいつもビビってやめる)のトランプ大統領は与しやすい相手と見なされているだろう。