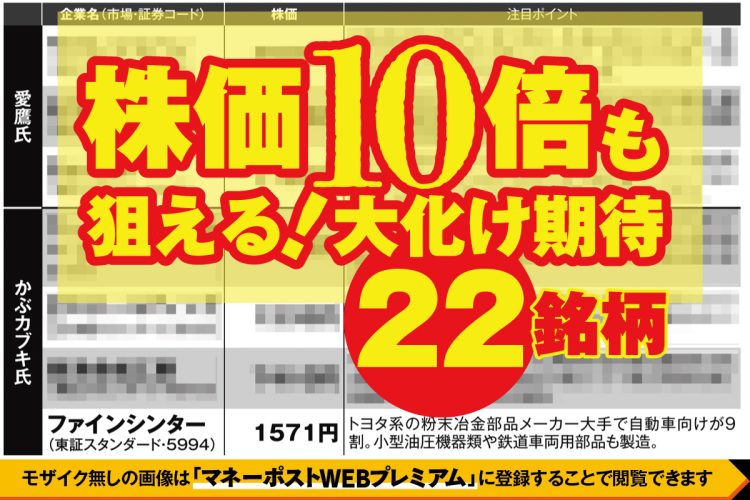日本の防衛産業に山積する課題とは(左から高市早苗・首相、小泉進次郎・防衛相/時事通信フォト)
対米公約で防衛費が大幅に増額され、防衛産業は“特需”に沸いている。高市早苗・首相が防衛装備輸出の規制を緩和し、世界に売っていく姿勢を見せていることも背景にある。そんな日本の防衛産業の今後の課題を探った。
危機が迫っていた防衛産業のサプライチェーン
世界的にも高い技術力を誇る日本の防衛産業だが、一方で残された課題も大きい。
日本では長く、米国からF-35など最新鋭装備を大量に購入する一方、その分、国産の防衛装備の予算が絞られてきた。そのため、防衛装備品の生産から撤退する企業が相次ぎ、防衛産業が少しずつ細ってきた。防衛問題研究家・桜林美佐氏の指摘は具体的だ。
「住友電工が航空機用レドームから撤退し、横浜ゴムは航空機用タイヤ、コマツは防衛車両、ダイセルは射出座席や火工品から事業撤退しました。ちなみにベンダー(下請け)の数はF-2戦闘機は約1万1100社、10式戦車は約1300社、護衛艦は約8300社ありますが、多数の企業が生産ラインを縮小したり、リストラを続けてきたわけです」
状況が大きく変わったのは2022年末だった。
岸田政権は米国の強い要請で防衛費を5年間で43兆円増額し、「GDP費2%」に引き上げる方針を決定。2023年には防衛生産基盤強化法を成立させ、自衛隊の装備品を製造する企業が事業継続困難になった場合、その生産ラインを国有化し、別の企業に委託する仕組みが盛り込まれた。
つい2年ほど前まで防衛産業のサプライチェーンはそれほどの危機に陥っていたのだ。
原因は、武器輸出三原則や5類型【※注】の制約の下、政府が長く武器輸出を事実上できなくしてきたことにある。
【※注/輸出を認める装備品を「救難」「輸送」「警戒」「監視」「掃海」の5類型に限っていること】
「本来、武器輸出には二つの効果がある。輸出で防衛産業を活性化させ、サプライチェーンを維持する。もう一つは外交のツールです」(同前)