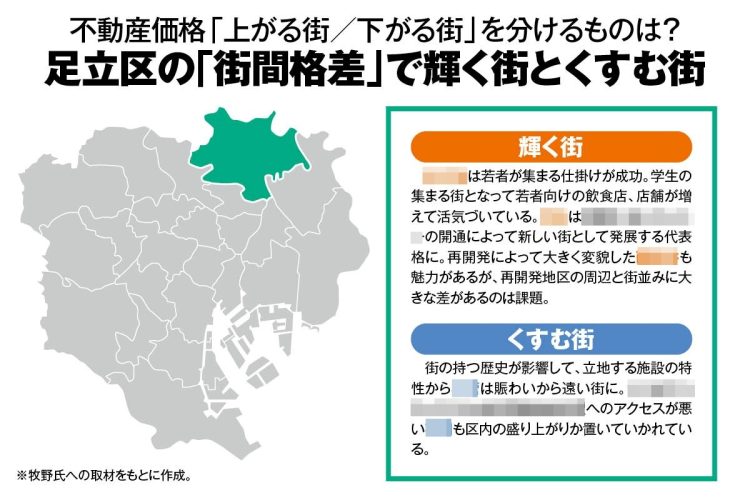世界を翻弄するトランプ関税の行き着く先は(SPUTNIK/時事通信フォト)
高関税政策を繰り返してきたアメリカは、第二次世界大戦の「反省」から、戦後は自由貿易体制の守護者となった。しかし、「アメリカ・ファースト」を掲げるトランプ政権はその立場を根底から覆そうとしている。歴史作家の島崎晋氏がアメリカ高関税政策の歴史を検証、20世紀初頭から第二次世界大戦に至る道筋を振り返る。【前後編の後編。前編から読む】
【20世紀初頭】「輸出は減らしたくないが、輸入も増やしたくない」
高関税政策にはどうしても物価の上昇がつきまとう。大衆の不満の高まりは避けられず、それを吸収し、1913年に成立した民主党のウィルソン政権のもとでアンダーウッド関税法が成立する。あらゆる輸入品に対する関税を撤廃もしくは低減させながら、個人所得税の導入により関税収入の減少分を補うというもので、平均関税率は26%まで引き下げられた。
これにより社会・経済上の混乱は短期間のうちに収束に向かったが、第1次世界大戦(1914〜1918年)の勃発と戦争特需を経て、戦後不況が到来すると、再び世論の動向が変わった。
輸出を減らしたくないが、輸入も増やしたくない。身勝手ではあるが、アメリカ国内の各業界の要望を集約すれば、そのようになる。このような流れを受け、1920年代のアメリカでは共和党政権が3代続き、保護貿易主義への復帰が鮮明となった。
新たな関税法の第1弾は1921年制定の緊急関税法とその翌年9月に成立したフォードニー・マッカンバー関税法(22年関税法)である。国際競争力の強い自動車の関税率が25%に引き下げられ、農家が必要とする農機具、結束用縄、カリ肥料が免税となったのを例外として、他の関税はのきなみ引き上げられた。なかにはコールタール生産物や染料、砂糖のように禁止的高関税を課された産品もあった。
22年関税法の特筆すべき点は、条件付きながら大統領に関税調整の権限を与える条項(同法315から317条)が加えられたことである。その内容は以下の通りだ(広島大学平和科学研究センター「IPSHU 研究報告シリーズ 研究報告No.33(2024年11月)」所収の鹿野忠生(広島大学総合科学部・同平和科学研究センター兼任)・橋本金平(広島大学大学院社会科学研究科)両氏による『現代世界経済秩序の形成とアメリカ海軍の役割 —世界史の全体構図からみた「太平洋戦争」の歴史的 意味とその教訓—』より)。
【315条(屈伸関税条項)】内外の生産費格差を関税が均等化していない事実が発見された場合、大統領は関税率をその50%まで変更することができる
【316条】大統領はアメリカ企業の特許権等を侵害している製品の輸入を排除することができる
【317条(報復関税条項)】アメリカの輸出品を差別しているとみなされる国からの輸入品に対して大統領は従50%までの新規関税ないし追加関税を賦課するか、または輸入を排除することができる
この3条はその後の関税法で多少の改変を加えられながら、現在も有効とされている。第2次トランプ政権下ではこれを乱用するばかりか、拡大解釈にも躊躇がないように映る。