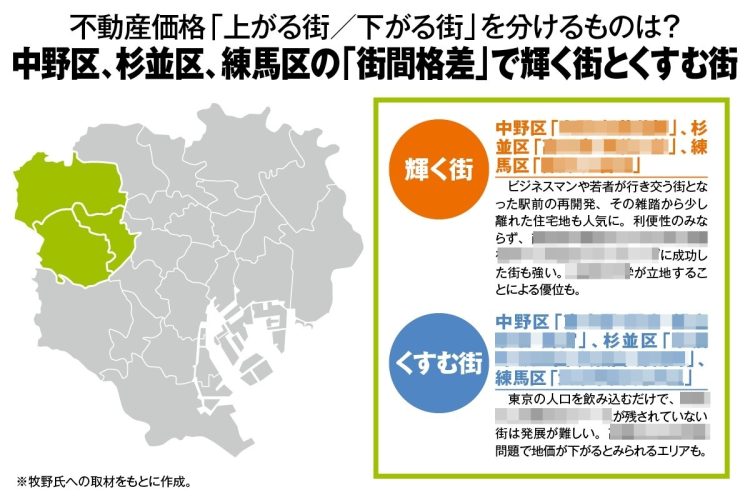トランプ関税は世界に何をもたらす?(AFP=時事)
同盟国に対しても「高関税」を課す第2次トランプ政権に世界が翻弄されている。個別交渉で「引き下げ」を約束しても、それがいつ実行されるかは不透明のままだ。この先、日本を含む世界経済はどこへ向かうのか。歴史作家の島崎晋氏が、1776年の独立宣言以来、何度も「高関税政策」を繰り返してきたアメリカの経済政策の歴史を振り返り、トランプ関税の“ルーツ”を検証する。建国後の関税をめぐる状況から、「南北戦争」を引き寄せ、内戦後も残った“対立軸”について振り返る。【前後編の前編】
目次
アメリカで今回並みの高関税を課した例は何度かあった
トランプ関税の行方はいまだ五里霧中で、このさきまだ一波乱も二波乱もありそうだが、世界全体としては、世界三大投資家のひとり、ジム・ロジャーズ氏がテレビ朝日のインタビューの中で応えた以下の見解に同意する人が多数派でないかと思われる。
「トランプ氏の関税政策は、アメリカや日本など世界中の国々にとって良いことは何一つありません。関税は、最終的には消費者へのさらなる税負担になるからです。トランプ氏は、関税を理解せずに発動させてしまった」(『グッド!モーニング』2025年8月12日放送分)
トランプ関税のもたらす結果を予想する上で参照すべきはやはり過去の事例だろう。歴史が短いと言われるアメリカでも、今回並みの高関税を課した例は何度かあった。トランプ関税の行く末を占うためにも、それらの背景と結果を検証したい。
【19世紀前半】産業保護を求める「米北部・西部」と、自由貿易を求める「南部」が対立
山川出版社刊行の『《世界歴史大系》アメリカ史1 17世紀〜1877年』所収の『ザ・エマージェンシー・オブ・ア・ナショナル・エコノミー1775-1815』(1962刊)から引用した統計表によると、イギリスからの独立達成当初、アメリカ連邦政府の歳入は完全な関税頼みだったようだ。1791年には実に100%、1801年になってもいまだ総歳入の83.1%が関税収入で占められていた。その後、所得税をはじめとする近代的な税制が整えられた結果、2023年の歳入に占める関税収入の割合はわずか1.8%にまで減少していた。
つまり、今回の関税の大幅引き上げは、建国以来、関税収入の占める割合が長期低下傾向にあるなか行われたというわけだ。もちろんその意図するところは歳入の増加ではなく、主に「国内産業の保護」である。実はその目的自体、19世紀初頭のアメリカ国内を二分するテーマだった。
独立からしばらくは「州」または時々の担当者により税率がバラバラだったアメリカで、初めて本格的な保護関税法が制定されたのは1816年4月のこと。イギリスが仕掛けてきた工業製品の猛烈なダンピング攻勢に対抗する手段としての立法だった。羊毛および絹製品、皮革、帽子、紙、砂糖などの輸入品目に平均20%の関税を課すという内容だったが、いざ施行してみると、国内の反応は両極端に分かれた。
この対立軸は国内産業の保護育成を優先させる保護貿易主義か、一次産品の輸出に主眼を置く自由貿易主義かと言い換えることができる。